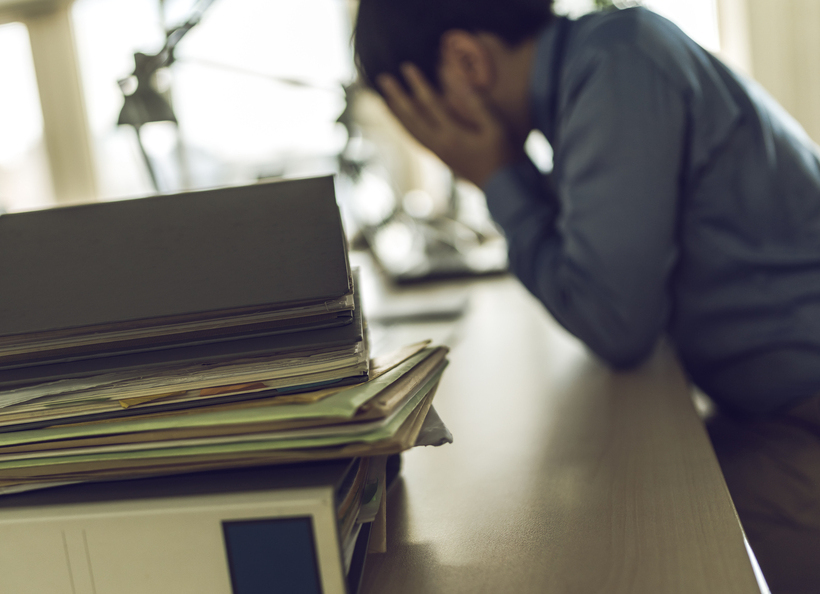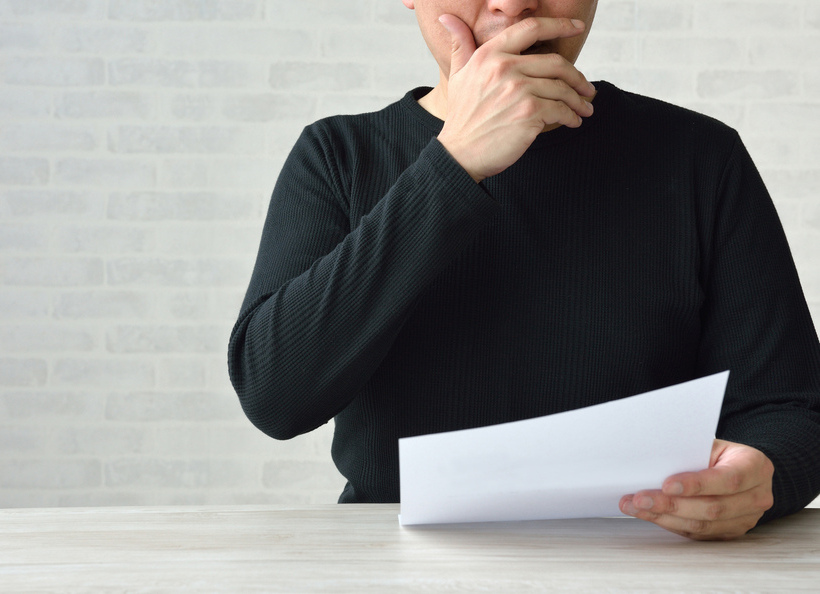
障害者雇用を進める企業にとって、解雇に関する法的知識は必須です。障害者であっても解雇自体は可能ですが、障害を理由とした差別的な解雇や、合理的配慮の相談を理由とした解雇は法的に禁止されています。
今回は、障害者雇用における「不当な解雇」とみなされる具体的な要件と、適切な解雇を行うための法的要件、さらに解雇以外の解決策まで詳しく解説します。
障害者雇用における「不当な解雇」とは

障害者であっても、解雇してはならない旨の法的な制限はありません。
しかし、障害者を不当に解雇した場合、解雇の撤回を求める訴訟や労働審判を起こされるリスクがあります。また、労働基準監督署からの指導や勧告の対象となる可能性や、助成金の受給に問題が生じる可能性もあります。
障害者を雇用する企業では、不当な解雇を防ぐ体制を整える必要があります。ここでは障害者の不当な解雇とみなされる要件を4つ紹介します。
障害者に対する差別による解雇
障害者雇用促進法により、障害を理由として労働者を差別することは禁止されています。
障害を理由とした解雇のほか、障害の有無で解雇の基準を設け、障害者にのみ不利な条件を課して解雇するのは不当な解雇です。例えば、解雇基準を障害者のみ引き下げて、障害者を解雇しやすい状況にする行為は認められません。
労働者の中から、障害があることを理由に、優先して障害者を解雇する行為も差別として扱われます。労働者を解雇する場合は、障害の有無にかかわらず平等な判断に基づいて行うことが求められます。
合理的配慮の相談を理由とする解雇
「障害者雇用促進法(正式法令名 : 障害者の雇用の促進等に関する法律)」に基づき、事業主は、障害者に対して合理的配慮をする義務があります。
合理的配慮とは、障害の特性に合わせた施設の整備や障害者を支援する人員の配置などです。障害者の体調を考慮した休憩時間の設定や障害者の特性に合わせた働き方の変更なども合理的配慮に含まれます。
事業主に過大な負担が生じる場合を除き、従業員である障害者から相談があれば、合理的配慮のための措置を講じなければなりません。合理的配慮に関する相談があったことを理由とした障害者の解雇は、不当な解雇に該当します。
配置可能な業務があるか検討せずに解雇
障害者を採用する段階で、他の従業員と比べて、作業に時間がかかる可能性があることは、企業側は把握しているはずです。そのため、予測されていた業務への影響は解雇理由にできません。
障害者を採用した後に、業務を遂行できないことが明らかになったときは、企業は、他の業務への変更や配置転換などを検討しなければなりません。配置転換などの検討をせずに障害者を解雇した場合は、不当な解雇として扱われます。
虐待の通報・届出を理由とする解雇
「障害者虐待防止法(正式法令名 : 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)」により、事業主による障害者虐待を発見した場合は、速やかに市町村または都道府県に通報することが義務づけられています。また、虐待を受けた障害者自身も通報できます。
障害者を雇用する事業者は、障害者の虐待に関する通報を理由に、障害者にとって不利益な扱いをすることは認められません。例えば、通報を理由とした解雇は禁止されています。
障害者雇用の解雇における要件

不当な解雇に該当しなければ、障害者であっても解雇できます。障害の有無に関係なく適用される3つの解雇の判断基準と要件を紹介します。
普通解雇の要件
普通解雇は、懲戒解雇に該当しない解雇です。勤務態度の不良や出勤状況の不良、能力不足などを理由とした解雇をいいます。
事業主は、「労働契約法」により解雇の制約を受けるため、理由があっても一方的な解雇はできません。まず、法律による制限にその解雇が該当しないことが普通解雇を行う条件です。
また、客観的に合理的な理由があると認められ、社会通念上相当な解雇であることを満たす必要があります。
懲戒解雇の要件
懲戒解雇は、懲戒処分の中でも最も重い処分です。業務上の横領や不正行為、ハラスメントなどの重大な規律違反に対して行われます。懲戒解雇は、次の要件を満たす必要があります。
- 就業規則において懲戒解雇の規定がある
- 規定されている懲戒解雇事由に該当する行為があったこと
- 就業規則に規定があるときは規定に基づき解雇手続きをすること
- 解雇の理由が客観的に合理的であり、社会通念上相当であること
- 過去の対応と照らし合わせて懲戒解雇の処分が重すぎないこと
整理解雇の要件
整理解雇は、会社の経営上、人員削減が必要となった場合の解雇を指します。事業縮小による解雇や経営悪化による解雇などが該当します。一般的な判例法理に基づくと、整理解雇で満たすべき要件は、次の通りです。
- 客観的に業務上において人員整理が必要であること
- 希望退職者の募集など解雇に至らないよう努力したこと
- 解雇対象者を選ぶ基準に合理性があること
- 従業員や労働組合と協議や交渉を十分に行ったこと
障害者の解雇に迷ったときに企業ができること

障害者雇用を進めたものの、採用後に問題が生じる可能性もあります。障害者の解雇を検討している場合、円満に解決するにはどうするべきか、3つの方法を紹介します。
弁護士・社労士に相談する
労働に関する問題は、労働や社会保険のプロである社会保険労務士への相談が考えられます。社会保険労務士は、社会保険の手続きのほか、人事や賃金に関する制度などのコンサルティングも行う専門家です。
労働条件や労働環境、社会保険関係などの障害者に関する労働の課題は、社会保険労務士に相談できます。
障害者の解雇について法的な相談をしたい場合は、法律のプロである弁護士への相談が考えられます。弁護士に相談する際は、過去の労働裁判の実績や障害者の就労に関する専門性を参考にしましょう。
障害者雇用や労働裁判に詳しい弁護士であれば、解雇の正当性や裁判の対策などを相談できます。
状況の改善を専門家に相談する
障害者雇用については、ハローワーク以外の公的機関に相談する方法もあります。
例えば、全国の地域障害者職業センターへの相談です。障害者職業カウンセラーが障害者雇用に関する支援を行っています。ジョブコーチの派遣による支援や精神障害者の雇用継続支援など、事業者向けの支援の相談もできます。
雇用している障害者を解雇するのではなく、職場環境の改善や適切な働き方の実現を目指す事業者向けの窓口です。障害者雇用の専門家に相談することで、職場環境に対する助言や就労機器の貸し出しなどによるサポートを受けられます。
出典:厚生労働省「障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~」
解雇せず、新たな働き場所を提供する
働く場所を新たに提供することで、障害者を引き続き雇用する方法もあります。障害者雇用を進めていこうと考えていても、施設の整備や働く環境の整備が難しいなど、障害者雇用がうまく機能していない企業において検討できる方法です。
具体的には、サテライトオフィスや農園のレンタルなど、民間の障害者雇用支援サービスの活用が考えられます。
農園型は、障害者が働ける場所として、企業に農園を貸し出すサービスです。農園には、障害者を支援するスタッフが常駐しており、障害者が安心して働ける環境が提供されています。
農園型の障害者雇用支援サービスの詳細は、こちらの記事で紹介しています。
まとめ
障害の有無に関係なく、企業は労働者の解雇について制限を受けます。ただし、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇については、要件を満たしていれば問題ありません。
ただし、障害者については、障害を理由とした解雇や障害に関する職場環境の見直しの相談を理由とした解雇などは認められていません。法的規制に注意しつつ、障害者雇用については慎重な取扱いが求められます。
自社での障害者雇用の整備が難しい場合は、農園型の障害者雇用支援サービスを利用する方法があります。農園型なら「めぐるファーム」の利用をご検討ください。
障害のある方が快適に働ける屋外ハウスを就業場所として提供しています。専門スタッフが業務をサポートしており、定着率は95%(※2024年12月時点)と障害のある方にとってより良い環境を提供しています。
本記コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。