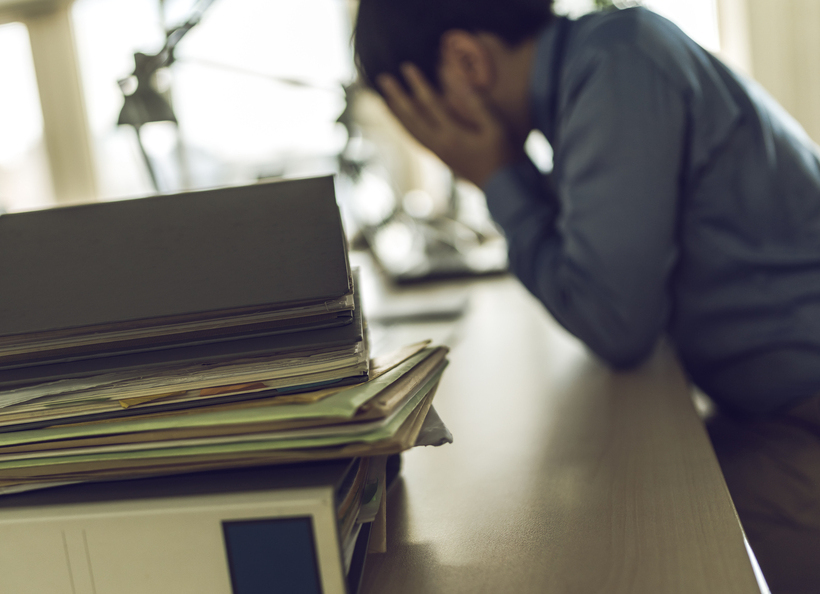障害者が安心して働き続けるためには、職場での理解と適切な支援が欠かせません。その架け橋となるのが「ジョブコーチ」です。ジョブコーチは本人と企業の双方に寄り添い、職場適応や雇用定着を支援する専門職として活躍しています。
今回は、ジョブコーチの役割や支援内容、利用方法、活用できる助成金制度について詳しく解説します。
ジョブコーチとは?

ジョブコーチとは、障害者が安心して働き続けられるように支援する専門職であり、「職場適応援助者」とも呼ばれます。厚生労働省が定める公的支援制度のもとで活動しており、障害者の職場定着を目的に、本人と企業の双方に寄り添いながらサポートを行います。
ジョブコーチの主な支援内容は、職場への訪問による作業指導や環境調整、同僚や上司への助言などです。
例えば、本人の障害特性に合わせた作業手順の工夫や、集中しやすい職場環境づくりを提案したり、周囲の職員に対して適切なコミュニケーション方法を伝えたりします。こうしたきめ細やかな支援を通じて、働く本人が安心して業務に取り組める環境を整えます。
また、ジョブコーチは企業側にとっても重要な存在です。障害者雇用の現場では、採用後の「ミスマッチ」や「早期離職」が課題となることがありますが、ジョブコーチが介入することで、双方の理解が深まり、安定した雇用関係の構築が可能になります。
このように、ジョブコーチは障害者の「働く」を支えると同時に、企業が多様な人材を受け入れるための橋渡し役として、社会全体の共生と職場のダイバーシティ推進に貢献しています。
ジョブコーチの具体的な支援内容

ジョブコーチは、障害者が安心して働き続けられるよう、本人への直接的な支援だけでなく、職場や企業への助言、さらに雇用定着を目的とした継続的なサポートを行います。
ここでは、その具体的な支援内容を3つの側面から解説します。
障害のある本人への支援
ジョブコーチは、障害者が職場で安心して働けるよう、業務内容や環境に応じた個別の支援を行います。
例えば、新しい業務を担当する際には、作業手順をわかりやすく説明し、習得するまで一緒に取り組みながらスキルの定着を図ります。必要に応じて、本人が実際に作業する姿を確認し、より効率的で無理のない方法を提案します。
また、慣れない職場での不安やストレスを軽減するため、日常的な相談支援や心理的なフォローも重要な役割のひとつです。励ましの声かけやポジティブなフィードバックを通じて、働く意欲を維持する支援をします。
さらに、障害特性に応じた仕事の進め方について、一緒に工夫しながら最適な方法を探ることもあります。例えば、注意力に課題がある場合にはチェックリストの導入を提案するなど、実際の業務に即した支援が行われます。
企業や職場への支援
ジョブコーチの支援対象は、障害のある本人だけではありません。職場全体が協力し合える環境づくりのために、企業や職場の同僚、上司への支援も行います。
具体的には、障害の特性や配慮の必要性について、わかりやすく説明したり、どのような声かけや指示が適切かをアドバイスしたりします。例えば、曖昧な指示が苦手な方には、具体的な行動を示すなどの工夫を提案します。
また、業務上のミスマッチを防ぐために、作業環境の改善や業務内容の調整、配置転換の検討なども助言します。これにより、本人が無理なく働けるようになるだけでなく、周囲の負担感も軽減され、職場全体の理解促進にもつながります。
雇用定着のための継続支援
ジョブコーチは、就職後も継続的にフォローを行い、職場への定着をサポートします。本人・企業・家族・支援機関の橋渡し役となり、情報共有や調整を行いながら、安心して働き続けられる環境を維持します。
また、職場でトラブルや課題が発生した際には早期に介入し、問題解決に向けたサポートを実施します。働く中で状況が変化しても、柔軟に支援内容を見直すことで、本人の働きやすさを継続的に確保します。
このように、ジョブコーチの支援は「働く前」「働くとき」「働き続けるとき」のすべての段階で寄り添う、総合的なサポート体制が特徴です。
ジョブコーチを利用する方法

障害者の職場定着を支援する「ジョブコーチ制度」は、企業にとって非常に有効なサポート手段です。
障害特性に応じた適切な働き方の提案や、職場内のコミュニケーション支援など、専門的な立場から支援が行われるため、障害者雇用が初めての企業にも安心感があります。
ここでは、企業がジョブコーチ支援を利用するための手順や、費用の有無について詳しく解説します。
企業が利用する手順
ジョブコーチ支援を希望する場合、まずは地域のハローワーク、または地域障害者職業センターに相談・申請を行います。申請には、障害者の雇用状況や業務内容、支援が必要な内容などの情報を提出する必要があります。
申請が受理されると、ジョブコーチが企業や職場に派遣され、対象となる従業員に対して直接的な支援を開始します。
なお、申込みから実際に支援が開始されるまでの流れや所要期間は、地域やセンターによって異なることがあります。スムーズな利用のためにも、事前に窓口へ相談し、スケジュールの確認を行うことが大切です。
費用負担の有無
ジョブコーチ支援は、厚生労働省が管轄する公的な制度の一環として実施されています。そのため、企業側および障害者本人には、原則として費用の負担は発生しません。公的支援として提供されることから、コスト面での不安を感じることなく活用できます。
ただし、支援には一定の制限もあります。派遣されるジョブコーチの人数や支援の期間には上限が設けられており、長期的または継続的なサポートが必要な場合には、公的支援のみでは十分ではない場合があります。
その際は、民間の就労移行支援事業所や定着支援サービスといった民間リソースを併用することで、より安定した支援体制を構築することが可能です。
ジョブコーチで活用できる助成金制度
ジョブコーチを活用する企業は、障害者の職場定着支援にかかる費用を軽減できる助成金制度を利用できます。
代表的なものに「訪問型職場適応援助者助成金」と「企業在籍型職場適応援助者助成金」があります。
ここでは、それぞれの助成金の概要を紹介します。
訪問型職場適応援助者助成金
訪問型職場適応援助者助成金は、地域障害者職業センターなどの外部機関からジョブコーチが派遣される場合に活用できる制度です。
障害のある本人が新たな職場に適応できるよう支援するために、企業が負担するコストを国が助成します。
訪問型では、一定期間ジョブコーチが職場を訪問し、本人や企業に対して作業指導や環境調整などの支援を行います。
企業在籍型職場適応援助者助成金
企業在籍型職場適応援助者助成金は、企業が自社内にジョブコーチを配置して支援を行う場合に利用できる助成制度です。
社内の人材がジョブコーチとして活動するための研修や支援時間に対して、助成金が支給されます。自社内で継続的に障害者支援を行う体制を整えたい企業にとって、有効な仕組みです。
これらの助成金はいずれも、障害者の職場定着を促進するための制度であり、利用には事前申請が必要です。ジョブコーチの導入を検討している企業は、申請要件や手続き方法を早めに確認しておくことで、より効果的に支援を受けることができます。
参考:
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「令和7年度4月版障害者雇用納付金関係助成金のごあんない」
厚生労働省「訪問型職場適応援助促進助成金」のご案内」
厚生労働省「企業在籍型職場適応援助促進助成金」のご案内」
まとめ
ジョブコーチは、障害者の「働く力」を支え、企業が安心して多様な人材を受け入れるための重要な存在です。公的制度や助成金を活用すれば、負担を抑えつつ安定した雇用環境を整えることができます。ジョブコーチの支援を上手に取り入れ、誰もが自分らしく働ける職場づくりを進めていきましょう。
さらに、公的支援だけでなく民間のサポートを活用することで、より充実した支援が可能になります。NEXT ONEが運営する「めぐるファーム」も、障害者の働く場づくりを支援する取り組みを行っています。
詳しくはめぐるファーム公式サイトをご覧ください。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。