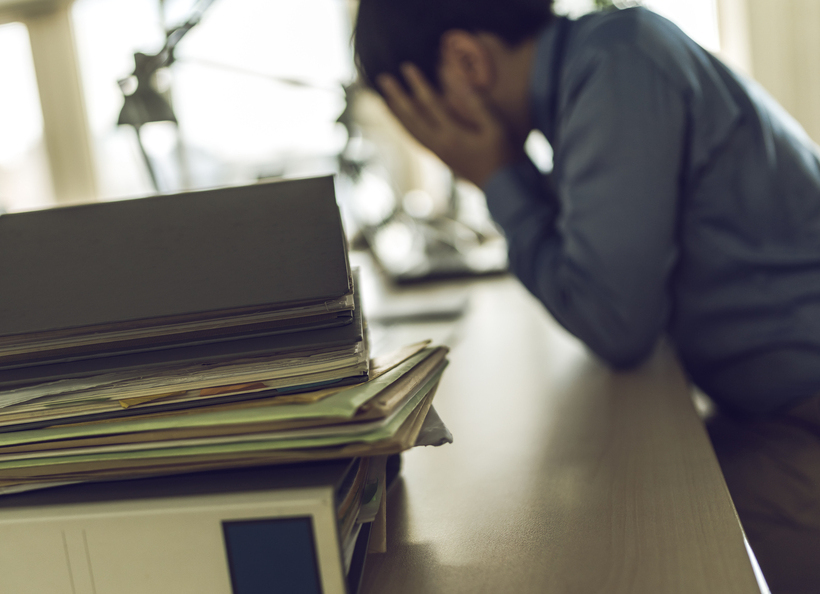無期転換ルール(5年ルール)は、雇用の安定を目的に設けられた制度であり、障害者を含むすべての有期契約労働者に適用されます。有期契約で働く方が5年を超えて同一企業で勤務した場合、申請によって無期雇用へ転換できる仕組みです。しかし、制度の理解不足や対応の遅れがトラブルを招くこともあります。
今回は、障害者雇用における無期転換ルールの基本と、企業が取るべき対応ポイントについて解説します。
無期転換ルール(5年ルール)は障害者雇用も対象

無期転換ルールは、雇用の安定を目的に設けられた制度であり、障害者を含むすべての有期契約労働者に適用されます。
ここでは、制度の定義や背景、そして対象外となるケースについて詳しく解説します。
そもそも無期転換ルールとは
無期転換ルールとは、有期労働契約が通算で5年を超えた場合に、労働者の申し込みによって期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)へ転換できる制度を指します。企業側はこの申し込みを拒否することはできません。
この制度の対象は、契約社員・パート・アルバイト・派遣社員など、有期雇用の名称を問わず広く及びます。重要なのは「通算5年」のカウントが同一の使用者(企業)との契約に限定される点です。つまり、別の企業に転職した場合は、通算期間はリセットされます。
また、契約期間が最初から6年以上の単一契約で更新がない場合は、雇用契約期間が5年を超えると申込権が発生しますが、無期労働契約に転換できるのは、7年目以降です。
無期転換ルールは、労働契約法第18条に基づき2013年4月1日に施行されました。その背景には、有期雇用の濫用防止や「雇止め」と呼ばれる契約更新拒否への対策、そして労働者の雇用安定を促進する目的があります。
特に、長期間にわたり同じ職場で働く人が、安定した環境で働き続けられるようにするための制度といえるでしょう。
無期転換ルールが除外されるケース
無期転換ルールはすべての有期契約労働者に平等に適用され、障害の有無にかかわらず、一般的な有期雇用と同様に5年を超えた時点で無期転換の権利が発生します。
企業は、障害のある従業員に対して制度の説明や申し込みのサポートを行い、安定した雇用環境を整備することが重要です。
ただし、一部の労働者については例外的に適用除外とされています。具体的には、次のようなケースが該当します。
- 国家公務員・地方公務員など、労働契約法の適用外となる労働者
- 船員など、労働契約法第18条の適用外となる労働者
- 年収1,075万円以上の高度専門職
- 定年後も引き続き雇用される有期雇用労働者
- 大学や研究開発法人に勤める研究者・教員(通算期間が5年から10年に延長される特例がある)
これらの特例を適用する場合は、都道府県労働局長による認定手続きが必要となります。認定を受けるには、事前に計画の作成や申請書類の提出などが求められ、一定の時間と準備が必要です。
障害者雇用における無期転換ルール(5年ルール)の対応ポイント

障害者雇用における無期転換ルールへの対応は、単なる制度遵守にとどまらず、企業の人材戦略や職場の多様性推進に直結する重要なテーマです。
障害のある社員が長期的に安心して働ける環境を整えるためには、無期転換制度をどのように運用するかを明確に定めておく必要があります。
ここでは、企業が押さえるべき具体的な対応ポイントを紹介します。
まずは基本方針を決める
無期転換ルールへの対応を検討する際、まず重要なのは「自社としてどのような方針を取るのか」を明確に決めることです。
制度上は労働者からの申込権が発生しますが、企業としてどのような姿勢で対応するかを事前に決定しておくことが、トラブル防止と人材活用の両立につながります。
基本的な選択肢は大きく3つに分けられます。
- 希望者全員の無期転換を認める方針
- 通算5年を超える前に雇止めを行い、無期転換を回避する方針
- 正社員登用制度などを活用して、一定の基準に基づいて登用を行う方針
それぞれの選択肢にはメリット・デメリットが存在します。
希望者全員の無期転換は雇用安定を促進する一方で、人件費や配置の柔軟性に影響が出る可能性があります。
反対に、無期転換を避ける方法は柔軟性を維持できますが、従業員のモチベーション低下や訴訟リスクを伴います。
正社員登用制度は中間的な方法であり、能力の高い人材を確保できる一方、基準の明確化と公平な運用が求められます。
企業は自社の経営状況や障害者雇用の方針に基づき、どの方針を取るかを慎重に検討し、文書化しておくことが重要です。
希望者全員を無期転換させる場合
希望者全員の無期転換を認める方針は、労働者に最も安心感を与える方法です。安定した雇用を提供できることで、離職率の低下や定着率の向上が期待でき、「長く働ける職場」として企業イメージの向上につながります。
一方で、雇用調整が難しくなり、成果や勤務態度に課題がある社員も無期雇用として残るリスクがあります。そのため、無期転換後に適用される就業規則を事前に整備することが不可欠です。具体的には、以下のような対応が求められます。
- 無期転換後にどの就業規則を適用するかを明確化(正社員規則・独自規則・契約社員規則の継続など)
- 転勤・配置転換条項の有無を確認し、必要に応じて見直す
- 定年規定を整備し、無期転換後も一貫した運用ができるようにする
近年では、ハマキョウレックス無期転換事件など、就業規則の整備不備が争点となった裁判もあり、無期転換社員への待遇や規則内容を明確に定めておくことが重要です。
すべての労働者に対して、職務内容や働き方に応じた合理的なルールを整備し、混乱を防ぐ体制づくりが求められます。
参考:厚生労働省「無期転換ルールに関する主な裁判例」
無期転換をそもそもしない場合
無期転換を回避する方針を取る企業では、通算5年を超える前に雇止めを行う必要があります。この方法のメリットは、企業の雇用調整機能を維持できる点にあります。
しかし、優秀な人材を失うリスクや、モチベーションの低下、さらには不当な雇止めと見なされる訴訟リスクが伴う点には注意が必要です。
法的には、雇用契約書や労働条件通知書に「通算5年を超えて更新しない」旨を明記しておくことが求められます。
また、2024年4月施行の労働基準法施行規則改正により、有期契約の更新回数や上限を採用時・更新時に明示する義務が新たに設けられています。これにより、雇用関係の透明性を高めることが重要になります。
さらに、過去の裁判例(博報堂事件など)では、雇用継続に対する期待が認められ、企業側の雇止めが無効とされたケースもあります。
したがって、障害の有無に関わらず「いつまで働けるのか」を明確に伝え、本人のキャリアプランと企業の雇用方針をすり合わせることが大切です。
参考:厚生労働省「無期転換ルールに関する主な裁判例」
正社員登用制度を導入する場合
正社員登用制度を導入する方法は、有能な人材を長期的に確保しつつ、組織の柔軟性を保つ現実的な選択肢です。特に障害者雇用においては、能力や意欲に応じてキャリアアップの道を提示することで、モチベーションの向上や職場定着につながります。
メリットとしては、優秀な人材を囲い込みつつ、すべての従業員を無期転換する必要がないため、組織運営の自由度を維持できる点があります。
一方で、登用されなかった社員に不公平感や不満が生じるリスクがあり、基準や手続きの明確化が不可欠です。
制度設計のポイントとしては、以下の事項を押さえる必要があります。
- 選抜時期は「無期転換申込権」が発生する前に設定する
- 登用基準や時期、非登用時の処遇を就業規則に明記する
- 雇用契約書や労働条件通知書に、登用制度の内容や更新上限を明示する
- 労働基準法第89条3号に基づき、「退職に関する事項」として必ず規則に盛り込む
このように、正社員登用制度は、障害の有無に関わらず公平性と透明性を持って運用することが重要です。企業が制度の趣旨を丁寧に説明し、評価・登用プロセスを明確にすることで、安心して働ける環境づくりと戦略的な人材活用を両立できます。
まとめ

無期転換ルールは、すべての有期雇用労働者に雇用の安定をもたらす仕組みです。企業は制度の趣旨を理解し、自社方針を明確化した上で、公平で透明性の高い運用を行うことが重要です。
無期転換ルール(5年ルール)への対応など、障害者雇用の体制構築に不安がある場合は、専門の支援サービスへサポートを依頼するのもひとつの方法です。制度を上手に活用し、誰もが安心して働ける職場づくりを進めていきましょう。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。