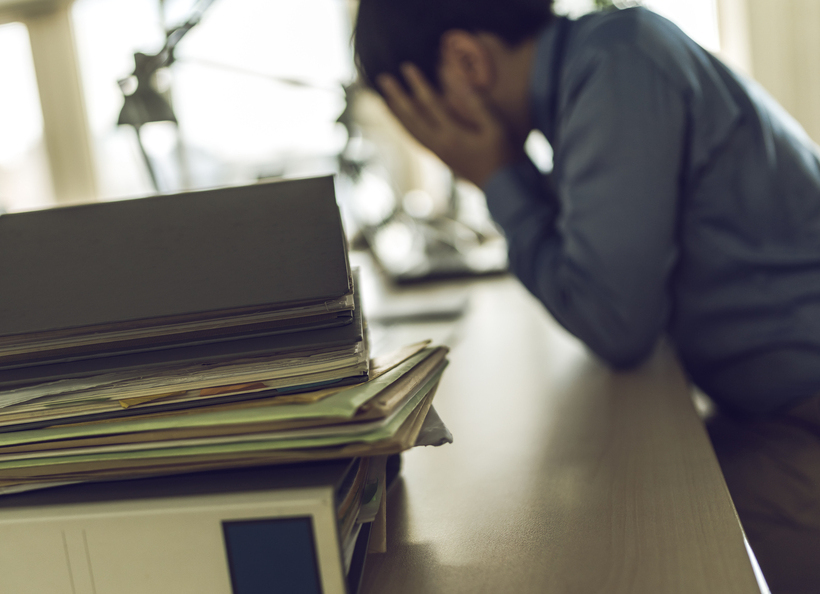障害と一口に言っても、その種類や特性は大きく異なります。職場で適切な配慮を行うためには、それぞれの障害の特徴を正しく理解することが欠かせません。今回は、障害の種類と特徴、そして支援のあり方について解説します。
障害の種類
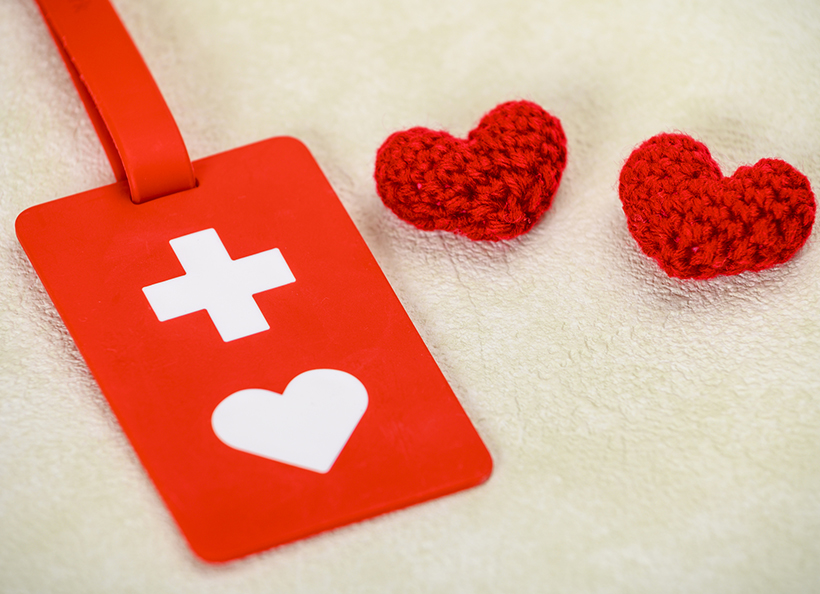
障害は大きく分けて「精神障害」「知的障害」「身体障害」の3種類に分類されます。それぞれの特徴を理解することが、職場での適切な配慮につながります。
| 障害の種類 | 主な特徴 |
|---|---|
| 精神障害 | うつ病、統合失調症、双極性障害などが含まれ、気分や思考、行動に影響が出ます。環境調整や周囲の理解によって、生活や就労の質が大きく変わります。 |
| 知的障害 | 発達の過程で知的機能に制約があり、学習や判断に影響が見られます。社会生活において、適切なサポートが必要になる場合があります。 |
| 身体障害 | 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など多岐にわたります。物理的な支援や環境整備が必要ですが、補助器具や設備の工夫により自立を支援できます。 |
主な精神障害の特徴

精神障害にはさまざまな種類がありますが、職場や日常生活でよく見られる代表的なものとして「うつ病」「統合失調症」「双極性障害」があげられます。これらの障害は、症状の現れ方や支援のポイントが異なるため、正しい理解が重要です。
ここでは、それぞれの特徴や支援の考え方について解説します。
うつ病
うつ病は、強い気分の落ち込みや意欲の低下が長期間続くことで、仕事や家庭生活に影響を及ぼす精神障害です。本人の努力や性格の問題ではなく、脳の働きやストレス環境などが影響していることを理解することが大切です。
主な症状として、何をしても楽しいと感じられない、集中力の低下、疲れやすさ、睡眠や食欲の変化などがあげられます。仕事面では、業務への意欲が落ちたり、ミスが増えたりすることもあります。このようなときには、業務負担を一時的に軽減し、十分な休養を確保することが回復への第一歩です。
また、うつ病の人に対しては「頑張って」「気持ちを切り替えて」などの励ましは逆効果になることがあります。本人のペースを尊重し、必要に応じて専門家の治療や相談につなげるなど、状況に応じたサポートを行うことが大切です。
統合失調症
統合失調症は、幻覚や妄想、思考のまとまりにくさなどが見られる精神障害です。発症の原因は完全には解明されていませんが、脳内の情報伝達のバランスが崩れることが関係していると考えられています。
症状には「陽性症状(幻聴・妄想など)」と「陰性症状(意欲低下・感情の平板化など)」があります。治療の基本は服薬管理であり、抗精神病薬によって症状を安定させることが可能です。また、規則正しい生活リズムを維持することも再発予防に役立ちます。
統合失調症は誤解や偏見を受けやすい病気ですが、適切な治療と支援があれば多くの人が安定した社会生活を送ることができます。周囲が症状を正しく理解し、安心して話せる環境を整えることが重要です。
双極性障害
双極性障害は、気分が高揚する「躁状態」と、落ち込む「うつ状態」を繰り返す精神障害です。感情の波が激しいため、仕事や人間関係に影響が出ることがあります。躁状態では活動的になりすぎて睡眠を取らなくなったり、判断力が低下して衝動的な行動を取ったりすることがあります。
治療の中心は薬物療法で、気分の変動を安定させる「気分安定薬」などが用いられます。
また、状態に応じて働き方を柔軟に調整することが大切です。躁状態のときは過集中や過労を避け、うつ状態のときは無理をせず休養を取るなど、バランスの取れた生活を心がける必要があります。
さらに、過度なストレスや刺激が症状を悪化させる場合もあるため、環境を整え、安心して過ごせる職場づくりが求められます。周囲が病状を理解し、協力し合うことで、本人の安定した社会生活を支えることができます。
主な知的障害の特徴
知的障害は、知的能力や適応行動に制約がある状態を指し、日常生活や社会生活で支援を必要とする場合があります。知的障害といってもその程度や得意・不得意は個人によって異なり、支援のあり方も人それぞれです。
ここでは、学習の特性、社会生活上の課題、そして就労における配慮という3つの視点から、その特徴と支援のポイントを紹介します。
学習の特性
知的障害のある方は、他者とのコミュニケーションや社会的なルールの理解が難しい場合があります。新しい知識や作業手順を身に付ける際には、一般的なペースよりもゆっくりと、段階的に学べるよう配慮することが求められます。そのため、指示や説明は簡潔で具体的に伝えることが効果的です。
また、文字や抽象的な表現よりも、図や写真などの視覚的なサポートを取り入れることで理解が深まりやすくなります。マニュアルやチェックリストなどを活用し、作業内容を見える化することも有効です。
さらに、繰り返しの練習や定期的な確認を通じてスキルの定着を促進することができます。
社会生活上の課題
知的障害のある方は、言葉のニュアンスや相手の気持ちを読み取ることが苦手なこともあり、誤解やトラブルにつながることも少なくありません。
こうした課題を防ぐには、あらかじめ行動やルールを明確にしておくことが重要です。例えば、あいさつの方法、報告・連絡・相談の手順、勤務中のマナーなどを具体的に示し、必要に応じて繰り返し伝えることで安心して行動できるようになります。
また、本人が信頼できる上司や同僚が身近にいることで、困ったときに相談しやすくなり、安定した人間関係を築くことができます。安心できる人間関係の中でこそ、自分の力を発揮し、成長できるのです。
就労における配慮
知的障害のある方が長期的に働くためには、適性に応じた業務の配置と、理解しやすい環境づくりが欠かせません。
複雑な作業よりも、手順が明確で繰り返し行う仕事のほうが力を発揮しやすい傾向があります。そのため、作業内容を細分化し、一つずつ確実にできるようサポートすることが効果的です。
また、作業マニュアルをイラストや写真入りで作成したり、支援員や職場のサポーターが定期的にフォローしたりすることで、安心して働くことができます。業務中に迷ったときすぐに相談できる環境があると、ミスの防止や不安の軽減にもつながります。
さらに、知的障害のある方は、得意分野において高い集中力や持続力を発揮することがあります。単純作業の精度が高い、ルーティンワークを丁寧にこなすなどの強みを活かすことで、本人や職場にとっても良好な関係を築けます。
主な身体障害の特徴

身体障害は、視覚・聴覚・肢体など身体機能の一部に制限が生じ、日常生活や社会活動において一定の支援や環境整備を必要とする状態を指します。その特性は障害の部位や程度によって異なりますが、適切な配慮や工夫により、多くの方が職場や地域社会で活躍しています。
ここでは、視覚障害・聴覚障害・肢体不自由の3つの代表的な身体障害について、それぞれの特徴と支援のポイントを紹介します。
視覚障害
視覚障害は、視力や視野の障害により、見え方に制限がある状態を指します。視覚による情報取得が困難な「全盲」から、見える範囲が狭い、明暗の区別が難しいなどの「弱視」まで、程度や症状はさまざまです。そのため、一人ひとりの見え方に合わせた支援が求められます。
職場では、点字や音声読み上げソフト、拡大読書器などの支援技術を活用することで、情報へのアクセスが容易になります。また、資料やメールはデジタルデータで提供すると、読み上げソフトとの併用が可能です。
環境面では、机や通路に障害物を置かない、段差に明確な色分けをするなど、安全に移動できるような配慮が必要です。さらに、案内表示を立体文字や音声案内に対応させるなど、視覚以外の感覚で情報を得られる工夫が効果的です。
聴覚障害
聴覚障害は、音の聞き取りや会話の理解に制限がある状態を指します。軽度の難聴から、音声による情報取得が困難な状態まで幅があります。
情報共有の方法を工夫することが重要で、例えば筆談や手話、チャットツールなどの文字によるコミュニケーションは非常に有効です。オンライン会議ではリアルタイム字幕を利用する、対面の会話では口元が見えるようマスクを外す、あるいは透明マスクを使用するなど、状況に応じた対応が求められます。
また、研修や会議などの場では、手話通訳や要約筆記などの「情報保障」を行うことで、平等に内容を理解できるようになります。周囲が配慮と理解を持って接することが、安心して働ける職場づくりにつながります。
肢体不自由
肢体不自由は、手足や体幹の動きに制限がある状態を指します。原因として、脳性まひや脊髄損傷、交通事故などによる外傷があげられます。症状や影響の範囲は人によって異なり、歩行が困難な方、手先の動きに制約がある方など、必要な支援内容も多様です。
職場では、車椅子対応の通路やトイレの整備、机の高さ調整など、物理的なバリアフリー化が不可欠です。移動の負担を減らすために、在宅勤務やテレワークなど柔軟な働き方を取り入れることも効果的です。
さらに、作業環境の工夫によって、多くの方が自分の能力を活かせます。例えば、PC操作を音声入力や特殊マウスで行う、重い物の持ち運びを他の職員がサポートするなど、チームでの協力体制を築くことが重要です。
まとめ
障害にはさまざまな特性があり、それぞれに応じた理解と支援が不可欠です。精神障害では心の状態への配慮、知的障害ではわかりやすい指示やサポート、身体障害では環境整備や支援技術の活用が重要となります。
障害者雇用をこれから進める、あるいは現在進めている企業様は、障害の特性や必要な配慮に合わせた取り組みを行いましょう。誰もが安心して働ける職場づくりを一歩ずつ進めていくことが大切です。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。