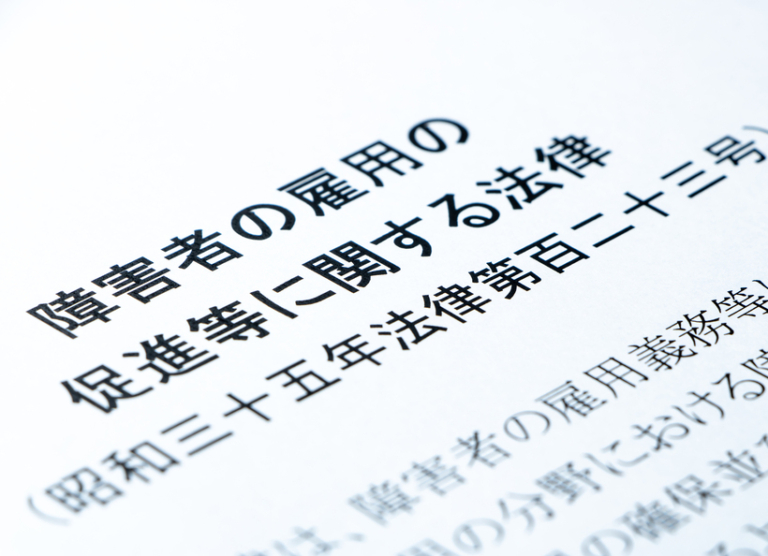障害者雇用を進めようと考えているものの、制度や対象範囲などがよくわからないと感じていませんか。障害者雇用成功のためには、関連する法律の概要を把握しておくことも重要です。
今回は、障害者総合支援法について、概要や押さえておくべきポイントについてわかりやすく解説します。
障害者総合支援法とは?

障害者をサポートする法律に、障害者総合支援法(正式法令名:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)があります。どのような法律なのか、まず、概要や制定の背景について説明しましょう。
なお、障害者の安定就労についての法律としては、障害者雇用促進法(正式法令名:障害者の雇用の促進等に関する法律)があります。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
法律の概要
障害者総合支援法は、障害のある方が基本的人権を持つ個人として、日常生活や社会生活を送れるよう支援を定めた法律です。
障害者に必要な福祉サービスの給付や地域生活支援事業などの総合的な支援が制定されています。
以下が基本理念として定められています(第一条の二)。
「障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。」
引用:e-GOV「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
障害の有無にかかわらず人々が共生できる社会にすること、障害があっても社会に参加する機会が確保されることが目的であることがわかります。
障害者総合支援法の対象になるのは、以下に該当する場合です。
- 身体障害者、知的障害者、発達障害を含む精神障害者で18歳以上の方
- 身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害を抱える18歳未満の児童
- 政令に定める難病で障害があると認められる方(難病患者)
法律制定の背景と変遷
障害者総合支援法は、2013年に施行された法律です。法律の成立までにさまざまな経緯がありました。2000年から2013年にかけての制定までの経緯を説明します。
2000年|社会福祉基礎構造改革
現行の障害者総合支援法は、2000年の社会福祉基礎構造改革の流れを汲んだ法律です。2000年以前は、社会福祉事業は基本的に行政に決定権がありました。
そこで、社会福祉のあり方を行政が決めてしまうのではなく、利用者の意思でサービスを選択できるように制度の方針を変えたのが社会福祉基礎構造改革です。
社会福祉サービスの量や質を良くすることを目的に、福祉サービス事業の規制緩和が行われました。これにより、民間企業の社会福祉事業への参加が促進されました。
2003年|支援費制度の開始
サービスの利用者自らが選択できる仕組みは、2003年の支援費制度の施行で実現します。支援費制度は、現行の障害者総合支援法の基礎となったものです。
これまで適用されてきた障害保健福祉施策とは異なり、より充実したサービス内容をもって開始されました。しかし、数年で財源不足やサービス利用料の地域差などが問題となり、改正が迫られます。
2006年|障害者自立支援法の施行
支援費制度の課題を踏まえ、改正法として2006年に施行されたのが障害者自立支援法です。障害者が、地域社会で就労などを行い自立して生活できるように制定されました。
それまで存在していた障害者の区分がなくなり、すべての障害者が同様の支援を受けられる内容になります。しかし、多くの障害者が該当する低所得世帯にも1割の負担を課す制度で、障害者の負担が増加する形になりました。
障害者自立支援法の問題点は、サービス提供事業者にも不評を買ってしまいます。
2013年|障害者総合支援法の施行
2006年に施行された障害者自立支援法の改正により、2013年に障害者総合支援法が施行されました。障害者自立支援法の違憲訴訟に対し、訴訟の和解で交わされた基本合意に基づいて行われた改正でした。
障害者自立支援法から障害者総合支援法になったことで、障害者の自立ではなく、基本的人権を有する個人の尊厳に表現が変更されます。障害者との共生や社会参加の機会創出を重視した基本理念になりました。
改正により、障害者の範囲に難病患者が加わったほか、地域生活支援事業が明記されるなどの変化がありました。
障害者総合支援法の具体的な支援内容

障害者総合支援法では、自立支援給付と地域生活支援事業が支援内容として定められています。雇用制度に直接関係する内容ではありませんが、合理的配慮を考える上でヒントになるかもしれません。
合理的配慮については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
自立支援給付
自立支援給付は、障害がある方が社会生活や日常生活を送れるようにサポートする経済面での支援です。訓練等給付や介護給付、自立支援医療、相談支援などのサポートがあります。
訓練等給付は、障害のある方の自立や就労などを支援するものです。就労定着支援や生活訓練、自立生活援助などが含まれます。
介護支援は、介護を必要とする障害者の日常生活をサポートするものです。居宅介護や生活介護、施設への短期入所や入所支援などが含まれます。
参照:
厚生労働省「障害者総合支援法が施行されました」
厚生労働省「障害者総合支援法の給付・事業」
地域生活支援事業
地域生活支援事業は、障害の有無にかかわらず地域社会で円滑に生活を送れるサービスにかかわるものです。都道府県や市区町村が提供する支援で、自治体ごとにサービス内容が異なります。
代表的なものに、地域住民に対する障害者の理解促進研修、障害のある方を対象とした相談支援事業、成年後見制度利用支援事業などがあります。
これまでの支援事業などについては、厚生労働省「地域生活支援事業」で紹介されています。
障害者総合支援法について人事が押さえるべきポイント

障害者総合支援法の理解は、障害者雇用を成功させるサポートになります。実務面では、次の2つのポイントを押さえておきましょう。
2024年の改正点を確認する
障害者総合支援法において、障害者雇用に関連するものとして、2024年に3つの改正がありました。以下、各改正点について説明します。
1.就労選択支援の創設
障害者の希望や適性を踏まえ、ハローワークが実施する就業指導を通じて、就労アセスメントを行います。この制度は、障害者の一般就労への移行や定着を支援することも目的としています。
2.短時間労働者の雇用算定率の見直し
障害者雇用促進法において、雇用義務があるのは所定労働時間が20時間以上の労働者です。しかし、精神障害者など障害特性によっては、長時間労働が難しいケースもあります。
特例として、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者や重度身体障害者などについては、事業主が雇用率に算定できるようになりました。
3.障害者雇用調整金などの見直し
障害者の法定雇用率を達成した企業の超過人数分の調整金単価が調整により引き下げられ、雇用継続などの取組支援として助成金が創設されました。
改正のタイミングと内容を確認する
障害者総合支援法は、3年ごとの改正が定められている法律です。従来のサービスが撤廃となったり、新たなサービスが創設されたり、改正のたびに大きな変化があります。
2024年の障害者雇用に関連する障害者総合支援法の改正に触れましたが、2024年には雇用以外にもさまざまな改正が行われています。
障害者雇用を成功させるには、関連する障害者総合支援法の改正タイミングを把握しておくことが重要です。改正案の提出があったタイミング、施行のタイミングで概要を確認しておくことをおすすめします。
まとめ
障害者総合支援法は、障害のある方が尊厳をもって日常生活や社会生活を送れるように支援内容を定めた法律です。身体障害者、知的障害者、発達障害者、難病患者を対象にしており、自立支援給付と地域生活支援事業が定められています。
障害者総合支援法への理解は、障害者雇用を成功させるためにも重要です。3年ごとに改正される内容には、障害者雇用に関するものも含まれます。2024年には、雇用算定率や障害者雇用調整金の見直しがありました。
障害者の雇用をスムーズに進めるなら、「めぐるファーム」もご検討ください。
「めぐるファーム」はNEXT ONEが管理・運営している施設内で、農業などの作業を通して障害のある方の就労をサポートする事業です。常駐するスタッフが、仕事の指導だけでなく、生活面の支援も行っています。
農業を通じた自立支援とスキルアップを通して、持続可能な社会の実現を目指しています。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。