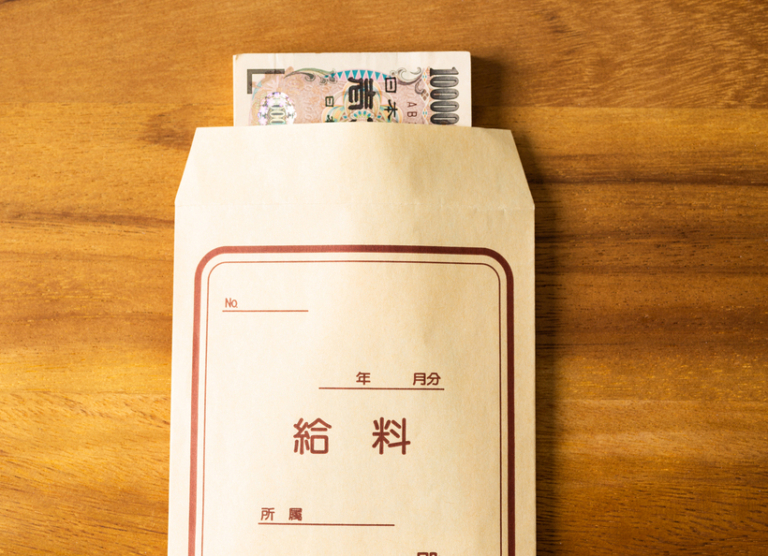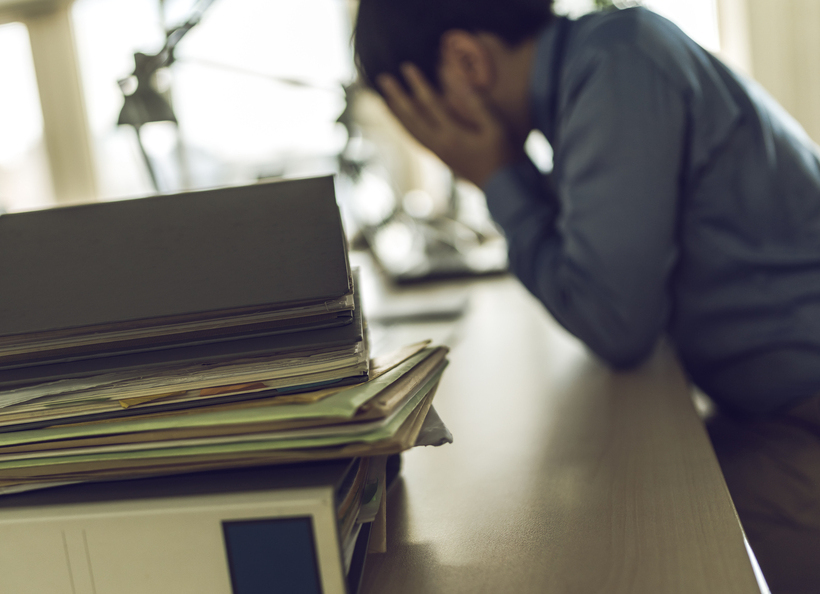障害者雇用を進める上で、多くの企業が直面する悩みのひとつが「給料をどう設定すべきか」という点です。障害者雇用には「障害者雇用促進法(正式法令名:障害者の雇用の促進等に関する法律)」や「最低賃金法」といった法律が関係しており、企業はこれらを遵守する義務があります。
今回は、障害者の平均給料データを紹介するとともに、給与を決める際の法的ルールや実務上のポイントを解説します。
障害者雇用の平均的な給料は?

障害者の平均的な給料は、障害の種類や職種・業種によって大きな違いが見られます。ここでは、厚生労働省が公表している「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」をもとに、障害者の平均的な給料について解説します。
出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」
身体障害者の平均給与
身体障害者の1か月あたりの平均賃金は235,000円で、他の障害種別と比べると比較的高い水準にあります。週30時間以上のフルタイム勤務では268,000円となり、安定した生活基盤を築きやすいのが特徴です。
一方で、20~30時間未満の勤務では162,000円、10~20時間未満では107,000円、10時間未満になると67,000円と大きく下がります。
職業別・産業別割合
産業別に見ると、身体障害者は製造業で21.3%と最も多く雇用されています。次いで卸売業・小売業が21.2%、サービス業が14.9%と続き、比較的多様な業種で活躍していることがわかります。
職業別では、事務的職業が26.3%と最多で、オフィスワークに従事する割合が高いのが特徴です。次に多いのは生産工程の職業(15.0%)、サービスの職業(13.5%)であり、製造現場や接客業務などでも多く雇用されています。
知的障害者の平均給与
知的障害者の1か月あたりの平均賃金は137,000円で、障害者雇用の中でも比較的低めの水準です。週30時間以上の勤務でも157,000円にとどまり、20~30時間未満では111,000円、10~20時間未満では79,000円、10時間未満では43,000円です。
産業別・職業別割合
知的障害者の雇用は、卸売業・小売業が32.9%と最も多く、次いで製造業(15.4%)、サービス業(13.2%)です。
職業別では、サービスの職業が23.2%で最も多く、飲食や清掃、接客補助など幅広い分野で活躍しています。次いで運搬・清掃・包装などの職業が22.9%、販売の職業が16.8%と続き、現場作業や接客の分野での比率が高いことがわかります。
精神障害者の平均給与
精神障害者の1か月あたりの平均賃金は149,000円で、知的障害者よりは高いものの、身体障害者と比べると低い水準です。週30時間以上の勤務では193,000円と比較的高水準ですが、20~30時間未満では121,000円、10~20時間未満では71,000円、10時間未満では16,000円と大きく下がります。
産業別・職業別割合
精神障害者の雇用先は、卸売業・小売業が25.8%で最も多く、製造業(15.4%)、サービス業(14.2%)と続きます。幅広い業種で受け入れが進んでいますが、特に販売や接客業務の現場に集中していることが特徴です。
職業別では、事務的職業が29.2%と最多で、オフィスワークに従事する割合が比較的高くなっています。次いで専門的・技術的職業(15.6%)、サービスの職業(14.2%)と続き、スキルや専門知識を活かした働き方をしている人も一定数います。
発達障害者の平均給与
発達障害者の1か月あたりの平均賃金は130,000円で、精神障害者と同程度の水準です。週30時間以上の勤務では155,000円ですが、20~30時間未満では107,000円、10~20時間未満では66,000円、10時間未満では21,000円と大きな差があります。
産業別・職業別割合
発達障害者雇用は卸売業・小売業に40.5%と大きく偏っており、次いでサービス業(14.6%)、製造業(10.2%)と続きます。
職業別に見ると、サービスの職業が27.1%で最も多く、飲食や接客に従事する人が多いのが特徴です。次いで事務的職業(22.7%)、運搬・清掃・包装等の職業(12.5%)と続きます。
障害者雇用の給料設定のルール

障害者を雇用する企業には、必ず守らなければならない「給料設定のルール」が存在します。法令を遵守し、公正な給与体系を築くためにも、以下の基本的なルールを確認しておきましょう。
障害者雇用促進法を遵守する
障害者雇用促進法第35条では、「障害者であることを理由として賃金の決定や待遇において不当な差別をしてはならない」と明確に定められています。
この不当な差別には、採用時の選考や配属、給与額の設定、昇進や降格、教育訓練の機会など、雇用全般に関わる要素が含まれます。
例えば、同じ能力をもつ障害者と健常者が同じ業務を行っている場合、障害を理由に給与を低く設定することは法律違反にあたります。
企業側は障害の有無ではなく、職務遂行能力や実績に基づいて公平に待遇を決定しなければなりません。
最低賃金法を遵守する
障害者雇用においても、最低賃金法は一般雇用と同じように適用されます。そのため、労働者と使用者が合意しても、最低賃金を下回る給与は無効となり、必ず法律で定められた最低額以上を支払わなければなりません。
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があり、地域別を下回った場合は50万円以下の罰金、産業別を下回った場合は30万円以下の罰金が科される可能性があります。
障害者雇用の最低賃金については、以下の記事でも詳しく解説しています。
障害者雇用における適切な給料設定のポイント
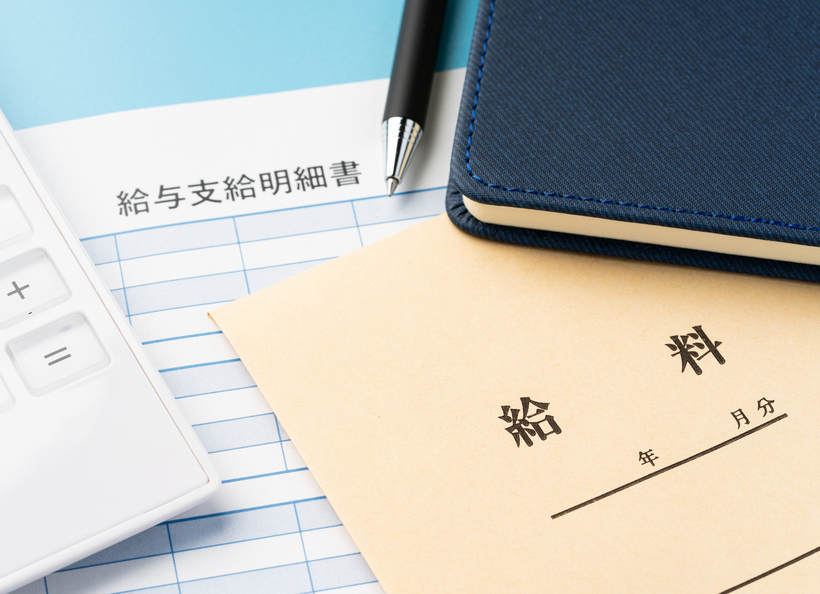
障害者雇用においては、適正な給与設定ができていないと、障害のある従業員本人だけでなく、他の従業員にも不満が生じやすくなります。給与面での不公平感が広がると、組織内の信頼関係が損なわれ、モチベーションの低下や離職率の上昇につながる可能性もあります。
そのため、障害者の給与を設定する際には「障害者だから」という理由ではなく、仕事内容や役割に基づいて決定することが重要です。
さらに、公平性と透明性を持った評価制度を整えることで、職場全体の士気を高め、安心して働ける環境を築けます。
ここでは、障害者雇用における適切な給料設定のポイントを4つ紹介します。
仕事内容と求める役割を確認する
給与を決める際に重要なのは、その従業員が担当する「仕事内容」と「役割」を確認することです。
障害の有無によって給与を上下させるのではなく、あくまで職務内容と責任範囲に基づいて適切に設定する必要があります。
例えば、事務作業やデータ入力など正確性が求められる業務、または接客や販売のように対人スキルが必要な業務など、それぞれの業務特性に応じて給与を決めていくことが公正な設定のために不可欠です。
さらに、従業員に期待する役割を明確にしておくことで、本人のやりがいにつながり、長期的に安定した雇用が実現するでしょう。
定期的に職務評価を実施する
障害者雇用においては、一人ひとりの能力や特性を正しく理解することが欠かせません。
そのために有効なのが「定期的な職務評価」です。職務評価では、担当業務の難易度や責任の大きさ、必要とされるスキルや経験を基準にして適切な給与を算出します。
職務評価を定期的に実施し、評価結果を給与に反映させることで、公平で透明性のある賃金体系の維持が可能です。
また、評価を通じて業務内容を見直し、新しい役割を与えることで、従業員が成長を実感できる職場環境を整えることにもつながります。
評価基準の透明性を確保する
給与を決める際の評価基準をあいまいにしてしまうと、不信感や不公平感が生じやすくなります。
そのため、あらかじめ「何をどのように評価するのか」を全社員にわかる形で明示することが大切です。
例えば、業務遂行能力や成果、出勤態度、スキルアップへの取り組みなど、具体的な評価項目を設定して共有することで、納得感のある給与体系を構築できます。
透明性を高めることで、障害の有無にかかわらず平等に評価されているという信頼感が生まれ、職場全体の一体感も強まります。
また、定期的に評価基準を見直し、時代や業務内容の変化に対応させることも重要です。
助成金を活用する
障害者雇用では、一般の雇用に比べて職場環境の整備や人材配置などにコストがかかる場合があります。
そこで活用したいのが、障害者雇用促進法に基づく「障害者雇用納付金制度」や各種助成金です。
例えば、障害者が働きやすいように作業施設を整備する際には「障害者作業施設設置等助成金」、介助者を配置する場合には「障害者介助等助成金」、職場での適応をサポートするためには「職場適応援助者助成金」など、目的に応じた制度が用意されています。
これらを上手に活用すれば、企業の負担を軽減しながら、障害者にとって働きやすい環境の整備が可能です。経済的支援を取り入れつつ、持続的な雇用を実現することが企業の成長にもつながります。
まとめ
障害者雇用における給与設定は、単に賃金額を決めるだけでなく、公平性・透明性・継続的な評価体制が重要です。適切な給与体系を整えることは、障害のある従業員が安心して働ける環境づくりにつながるだけでなく、職場全体の士気向上や企業の持続的な成長にも直結します。
しかし、実際の現場では「どのように業務を切り分けるべきか」「教育や定着支援をどう行うか」といった課題に直面する企業も少なくありません。そのような場合には、障害者雇用支援サービスを活用するのがおすすめです。
「めぐるファーム」は、NEXT ONEが管理・運営するスマート農園で、障害者が農作業などを通じて働く力を育み、将来的な一般企業への就労を目指しています。効率的で負担の少ない作業、充実した研修や定着支援など、多角的にサポートする仕組みが整っています。
また、企業側にとっても法定雇用率の達成やCSR・SDGsへの貢献など、多くのメリットがあるため、ぜひご活用ください。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。