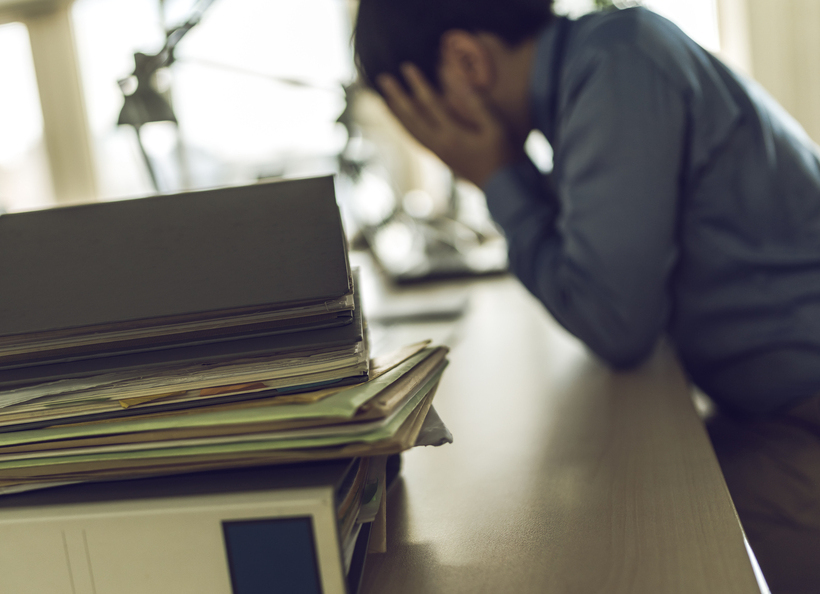障害者差別解消法(正式法令名:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が改正され、2024年4月1日からは事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されました。合理的配慮とは、どのような考え方なのでしょうか。
今回は、合理的配慮の意味や具体例、企業が直面する課題と対応策について解説します。職場全体をより働きやすくし、企業の社会的価値を高めるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
合理的配慮とは?

ここでは、「合理的配慮」の意味や具体例について解説します。
「合理的配慮」の意味
合理的配慮は、障害のある人が「社会的なバリア(障壁)を取り除いてほしい」と要求した際に、周囲が負担の大きすぎない範囲で適切な対応をすることを指します。
例えば、車いす利用者に対して段差のない通路を案内したり、聴覚に障害のある人に筆談や文字表示を用意したりするなどが該当します。
2021年に障害者差別解消法が改正され、2024年4月1日からは事業者による「合理的配慮の提供」が義務となり、働く場や日常生活のあらゆる場面で合理的配慮が求められるようになりました。
ここでは、合理的配慮について理解するためのポイントを3つ紹介します。
障害者と企業側との話し合いが必要
障害のある人が抱える困難さは一人ひとり異なり、必要とする配慮の内容も異なります。
そのため、画一的な対応ではなく「どの部分がセルフケアでは解決できず、どのような支援があれば業務がスムーズに進められるか」を双方で確認する必要があります。
また、企業にとって過度な負担とならない範囲で実行できるかどうかも重要なポイントです。きちんと話し合うことで、障害者本人のニーズと企業の実情のバランスを取りながら、現実的かつ効果的な合理的配慮が実現します。
障害者手帳の有無は関係ない
合理的配慮は、障害者手帳を持っているかどうかに関わらず必要とされます。
つまり、「身体障害、知的障害、精神障害」といった種別や、雇用形態が「障害者雇用枠か一般雇用枠」かに関係なく、その人の障害特性によって社会生活に困難を抱えている場合には対象となり得ます。
障害者からの申請が必要
合理的配慮は、障害者側から「助けを求める意思」が示されたときに提供されるものです。つまり、企業があらゆる配慮を用意する義務があるわけではなく、本人が「この部分で困難があるので支援してほしい」と伝えることが前提です。
本人が困っていても意思表示をしなければ、基本的に合理的配慮を提供する必要はありません。しかし、本人が気を遣って助けを求める意思表示をしない場合もあるでしょう。
そのため、事業者が気を付けたいのは、障害のある人が安心して申請できる雰囲気づくりや、相談窓口の整備をすることです。
合理的配慮の具体例
障害のある人が安心して働いたり学んだりするためには、障害の種類や本人の希望に応じた合理的配慮が必要です。
ここでは、合理的配慮がどのような場面で求められ、どのように対応するのが適切なのか、具体例を紹介します。
視覚障害の方への合理的配慮
視覚障害のある方からは、情報の取得や安全な移動をサポートする合理的配慮が求められることがあります。
例えば、出退社の通勤ラッシュを避けるため、フレックスタイム制の導入や時差通勤を認めることで、混雑を避けて安全に移動することが可能です。
また、「誰と話しているのかがわかりにくい」と悩む方には、声をかける際に「私は〇〇です」と最初に自分の名前を名乗ることで、安心感につながります。
業務においては、拡大文字の資料を用意したり、音声読み上げソフトや点字ディスプレイを導入したりすることで、情報へのアクセスを確保できます。
聴覚障害の方への合理的配慮
聴覚障害のある方にとって大きな課題となるのが、コミュニケーションの方法です。
例えば、入社手続きや面談の場面で、PCを用意して筆談することにより、意思疎通の齟齬を防ぐことが可能です。日常的なやり取りでも、筆談やメール、チャットツールを併用すれば、スムーズにコミュニケーションが取れるでしょう。
また、会議や研修の際に音声をリアルタイムで文字化するツールや、字幕機能付きのオンライン会議システムを導入することも有効です。
こうした工夫は聴覚障害のある人だけでなく、周囲の人にとっても情報が整理されやすくなるなど、副次的な効果もあります。
肢体不自由の方への合理的配慮
肢体不自由の方にとって障壁となりやすいのが、移動や作業環境です。
例えば、「面接会場・作業場所が遠い」「デスクが高くて作業しにくい」などがあげられます。面接時の移動の負担を軽減する方法としては、受付から近い部屋を面接会場にするのが有効です。
また、業務中の作業環境においては、必要な書類や備品を手の届く位置に配置したり、頻繁な移動を伴わない業務を担当してもらったりするといった配慮が有効です。
加えて、必要に応じてスロープや手すりを設置したり、机や椅子の高さを調整したりすることで、安全で快適に作業ができる環境を整備することが可能です。
こうした配慮は大規模な工事をせずとも、家具の配置換えやレイアウトの見直しで比較的簡単に実現できる場合があります。
結果として、職場全体の安全性や業務効率が向上し、すべての従業員にとって働きやすい環境づくりにつながります。
企業が合理的配慮を行う上での課題

合理的配慮は、障害のある人が公平に働ける環境を整える上で欠かせない取り組みです。しかし、企業がこれを実践するにあたっては、いくつかの課題が存在します。
【課題1】現場部署からの理解や協力が得られにくい
人事部や経営層が配慮の方針を示しても、実際に日常的に接するのは現場の従業員です。
そのため、「特定の従業員だけが柔軟な勤務時間を許されるのは不公平ではないか」「仕事の分担が偏るのではないか」といった懸念や不満が生じ、現場からの協力が得られにくいケースがあります。
【課題2】社内の障害への理解が不足している
障害の種類や特性は多岐にわたるため、社内に十分な理解が浸透していないと、誤解や不適切な対応につながる可能性があります。結果として、配慮の意図がうまく伝わらず、かえって職場内でのギャップが広がることもあります。
【課題3】個別対応にかかる時間・費用の負担
合理的配慮は一律の対応ではなく、障害の特性や本人の状況に応じた個別対応が求められます。
例えば、視覚障害者向けに音声読み上げソフトを導入したり、肢体不自由の従業員のためにスロープや手すりを設置したりするなど、企業にとって時間的・経済的な負担が伴う場合があります。
【課題4】障害のある従業員からの申し出が少ない
合理的配慮は本人からの申請が前提となるため、当事者が声を上げなければ必要な配慮が行われないことがあります。
その背景には、「周囲に迷惑をかけたくない」「特別扱いされたくない」といった心理的なハードルや、過去に申請が受け入れられなかった経験があることが考えられます。
適切な合理的配慮を行うための具体策

ここでは、先述した「企業側が抱えやすい課題」を解決し、適切な合理的配慮を提供するための方法について解説します。
合理的配慮に関する研修を実施する
合理的配慮を実現するには、経営層や人事部だけではなく、職場全体の理解が不可欠です。特に現場で一緒に働く従業員が正しく理解していなければ、制度や設備を整えても十分に機能しません。
そこで有効なのが、社内研修の実施です。研修では、合理的配慮の考え方を丁寧に伝え、具体的な対応事例を学ぶことで実践力を養えます。
自治体の助成金を活用する
合理的配慮を提供する際に「費用がかかる」という課題を感じる企業は少なくありません。しかし、多くの自治体では障害者雇用を推進するための助成金制度を用意しています。
例えば、北海道、栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、静岡県、大阪府、兵庫県、鳥取県、山口県などの自治体では、職場環境の整備にかかる費用を補助する事業を実施しています。
助成金を活用することで、スロープや手すりの設置、ICTツール導入といった環境改善を低コストで実現可能です。
助成金は年度ごとに内容が変わる場合があるため、最新情報を確認し、計画的に申請しましょう。
建設的対話を心がける
合理的配慮は、障害のある従業員からの申し出をきっかけに検討されることが多いですが、その際に重要なのが「建設的な対話」です。例えば、「前例がないからできない」「もし何かあったら責任が重い」といった理由で一方的に拒否するのは避けましょう。
対応が難しい場合であっても、代替案を提示したり、どの程度なら対応可能かを一緒に検討したりする姿勢が求められます。
対話を通じて信頼関係を築くことで、従業員は安心して相談でき、企業も現実的な範囲で最適な配慮を選択できます。
民間の障害者雇用支援サービスの利用も検討する
自社だけで合理的配慮を提供する体制を整えるのが難しい場合、民間の障害者雇用支援サービスを利用するのも手です。
NEXT ONEが運営する農園型障害者雇用「めぐるファーム」では、障害のある人が農作業に従事し、専門スタッフの支援を受けながら将来的な一般就労を目指せます。
最新の農業技術を取り入れている他、手順もマニュアル化していることから、障害者本人の身体的な負担を軽減できる点が魅力です。
また、法定雇用率の算入が可能で、採用後の教育や定着支援まで委託できるため、企業の負担も軽減できます。
まとめ
合理的配慮は、障害のある従業員が自分らしく働くために必要不可欠な取り組みです。
しかし企業にとっては「費用や時間の負担」「社内理解の不足」などの課題も存在します。そこで重要なのは、従業員への研修や自治体の助成金活用、建設的な対話の実践といった具体策を組み合わせ、無理なく持続可能な形で取り組むことです。
また、自社だけで抱え込まず、民間の支援サービスを利用することも検討してみてください。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。