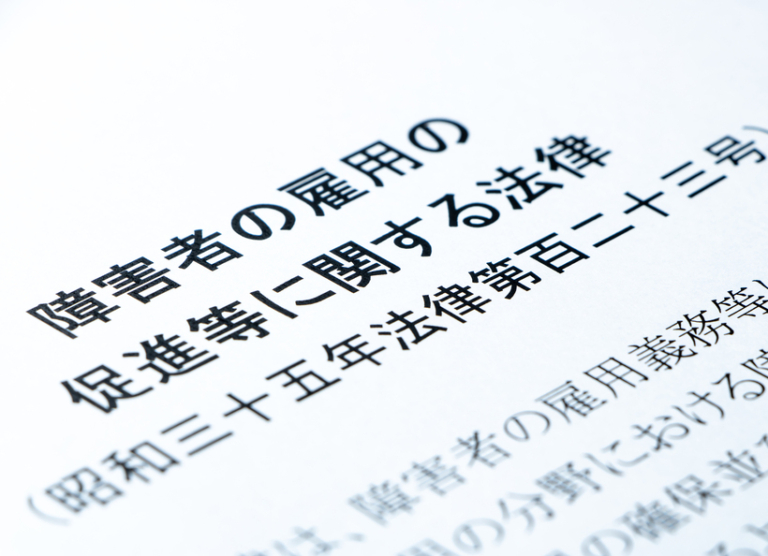「障害者雇用促進法(正式法令名 : 障害者の雇用の促進等に関する法律)」における除外率制度とは、障害者の就労が困難とされる業種について、除外率に相当する労働者の雇用が免除される制度です。この制度は全業種で廃止が決定しているため、除外率制度が適用される企業では、今から障害者の雇用を進めていく必要があります。
今回は、除外率制度の概要や対象業種別の除外率一覧、除外率の計算方法について解説します。
障害者雇用促進法の「除外率制度」とは?

障害者雇用促進法の「除外率制度」とは、障害者の就労が困難と認められる業種に対して、除外率に相当する労働者数の控除を認める制度です。
企業で雇用すべき障害者の人数を知るためには、定められた計算式によって雇用労働者数を計算する必要があります。その際に、雇用率の適用が困難と認められる業種については、除外率に相当する労働者数を控除できるのです。
障害者雇用促進法は、障害者が個々の特性に合った働き方ができるように、企業や自治体が障害者を一定の割合で雇用することを義務付ける法律です。従業員数が40.0人以上の企業には、法定雇用率2.5%以上の障害者を雇用する義務が発生します。
除外率が適用される企業では障害者の雇用義務が軽減されますが、障害者雇用の除外率制度は、平成14年の障害者雇用促進法の改正により段階的に廃止されることが決定されました。そして、現在まで計3回の引き下げが行われている状況です。
除外率が適用される企業では、このような状況を踏まえて正確な雇用計画の策定が求められます。
障害者雇用促進法について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
障害者雇用の業種別除外率の一覧

障害者雇用の除外率制度が適用される業種は、製造業や船舶運航業、高等教育、貨物運送業、医療職などです。
業務にあたり免許や資格などが必要であることや、安全性の確保が難しいことなど、主に障害者の方の就業が難しいとされる業種において適用されます。
以下の表は、令和7年4月時点の除外率対象業種一覧と、それぞれに適用される除外率です。
| 除外率が適用される業種 | 変更前の除外率 | 変更後の除外率 |
|---|---|---|
| ・非鉄金属製造業(非鉄金属第一次精製業を除く) ・倉庫業 ・船舶製造 ・修理業、船用機関製造業 ・航空運輸業 ・国内電気通信業(電気通信回線設備を設置して行うものに限る) | 5% | 廃止 |
| ・採石業、砂・砂利・玉石採取業 ・水運業 ・窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る) ・その他の鉱業 | 10% | 廃止 |
| ・非鉄金属第一次製錬・精製業 ・集配利用運送業以外の貨物運送取扱業 | 15% | 5% |
| ・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む) | 20% | 10% |
| ・港湾運送業 ・警備業 | 25% | 15% |
| ・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護医療院 | 30% | 20% |
| ・林業(狩猟業を除く) | 35% | 25% |
| ・金属鉱業 ・児童福祉事業 | 40% | 30% |
| ・特別支援学校(もっぱら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 45% | 35% |
| ・石炭・亜炭鉱業 | 50% | 40% |
| ・道路旅客運送業 ・小学校 | 55% | 45% |
| ・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 | 60% | 50% |
| ・船員等による船舶運航等の事業 | 80% | 70% |
今後は、上記の全業種において段階的に除外率が引き下げられ、最終的に廃止されることになります。しかし具体的な日程やタイミングについては、まだ正式には決まっていません。
出典:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
障害者雇用の除外率の計算方法

障害者雇用の除外率は、まず常用労働者数(※)から除外率に相当する労働者数を引き、その数に法定雇用率をかけて算出されます。
具体的な計算式は以下の通りです。
- 常用労働者数×除外率=除外人数
- (常用労働者数-除外人数)×法定雇用率=雇用義務のある障害者数
例えば、常用労働者数が1,000人、除外率が25%、法定雇用率が2.5%の企業の場合、雇用すべき障害者数は以下のように計算します。
- 1,000人×0.25=250人
- (1,000人-250人)×0.025=18.75人
よって雇用義務のある障害者数は、小数点以下を切り捨てて18人となります。
一方、除外率制度が適用されない業種の場合、雇用すべき障害者数の計算方法は以下の通りです。
1,000人×0.025=25人
雇用義務のある障害者数は25人であるため、除外率が適用される業種の企業では、7人分の雇用義務が免除されることになります。
※常用労働者は1人、短時間労働者は0.5人として算定する
除外対象の企業も今から準備を進めることが必要!
ここからは、除外率対象である企業も、今から障害者雇用の準備を進めるべき理由を解説します。
除外率制度は廃止が決定している
誰もが自分らしい生き方を追求できる社会を目指す「ノーマライゼーション」の考え方に基づき、平成14年の障害者雇用促進法の改正によって除外率制度の廃止が決定されました。
現在は、除外率制度の完全廃止へ向けた経過措置として段階的な引き下げが行われている状況で、過去に3回の引き下げが実施されています。
平成16年4月に最初の引き下げが行われた際は、除外率設定の対象であったタイヤ・チューブ製造業などを含む6つの業種が対象外となりました。
また平成22年7月には、有機化学工業製品製造業を含む5業種が除外率設定の対象から外されています。
さらに令和7年4月には、除外率が設定された全業種についてそれぞれ10%の引き下げが実施されました。
除外率が引き下げられると、これまで除外率設定の対象であった企業の雇用すべき障害者の数が増加することになります。
障害者の雇用数を上げることは重要ですが、まずは企業としてどのような障害者を雇用すべきであるかという方針を決めることがポイントです。
また障害者という枠をいったん外し、今組織で人手が求められる業務は何であるかを考えましょう。例えば「やる必要があるのに手が付けられていない業務」や「社員が就業時間外で行っている業務」などがあげられます。
なお、これらの業務を障害者に任せれば良いということではありません。今いる社員の中で担当者を決定し、その社員の業務を障害者に担当してもらうといった方法もあります。
障害者雇用の環境整備には時間・コストがかかる
障害者雇用は一朝一夕でできるものではありません。障害者が働ける環境を構築するためには時間やコストがかかるため、今から準備しておくことが重要です。
ここからは、障害者を雇用する際のステップ、障害者雇用にかかるコストについて解説します。
障害者を雇用するステップ
障害者の方を雇用し、就職後の長期の就労を促すための基本的なステップは以下の通りです。
- 障害者雇用の基礎知識について知る
- 障害者の採用計画を立てる
- 採用募集をする
- 採用選考をする
- 受け入れ体制を整える
- 長期雇用のための取り組みを行う
大きな流れは一般的な採用とあまり変わりませんが、法律による企業の義務や努力義務など配慮すべきポイントがあります。
また、障害者の方が職場に適応できずにすぐに辞めてしまったというケースは多くあるため、就労の定着を前提とした雇用が重要です。
障害者雇用を行う際は、障害者の方が働きやすい職場環境やサポート体制を整えるなど、入社後までの施策を考えておく必要があります。
障害者雇用の体制構築にかかるコスト
障害者の方を雇用するためには、職場の設備を整えるためにコストが発生します。例えば身体的に不自由な方を採用する際にはエレベーターやスロープ、手すりの設置などが必要です。
障害者雇用を行う企業では、国や自治体から助成金などのサポートを受けられる場合があります。代表的な助成金は以下の通りです。
- 特定求職者雇用開発助成金
- トライアル雇用助成金
- 障害者介助等助成金
- キャリアアップ助成金
例えば「特定求職者雇用開発助成金」を活用すると、最大240万円の助成金が企業に対して支給される場合があります。企業はこのような制度を利用することで、障害者の方をより採用しやすくなります。
出典:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」
障害者雇用の助成金について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
まとめ
障害者雇用促進法における除外率制度とは、障害者の雇用が一般的に困難と認められる業種について、障害者の雇用義務が軽減される制度です。
しかし除外率制度は、除外率設定の対象である全業種において、最終的には適用の廃止が決定しており、今後は企業の雇用すべき障害者数が増加することになります。
障害者雇用の環境整備には時間やコストがかかるため、除外率設定の対象となる企業は、早めに準備しておくことが重要です。
本記コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。