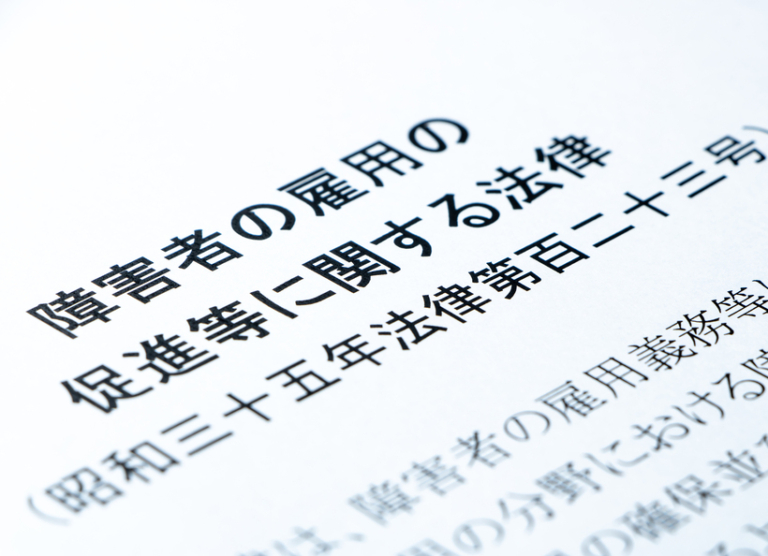障害者雇用において法定雇用率を下回っている場合は、足りない人数に応じて障害者雇用納付金を納める必要がありますが、取り組みが不十分とみなされた企業には行政指導が入る場合もあります。
今回は、「障害者雇用促進法(正式法令名 : 障害者の雇用の促進等に関する法律)」に基づく行政指導の概要をはじめ、実施の流れと判断基準、企業が取るべき対応策を解説します。法定雇用率を下回った場合の行政指導について理解を深めたい方は、ぜひご覧ください。
障害者雇用促進法の「行政指導」とは

障害者雇用促進法では、常用労働者が40名以上の企業(令和7年6月時点)に対して、従業員に占める障害者の割合を「法定雇用率」以上にすることが義務付けられています。
この法令により、法定雇用率の対象となる企業は、「障害者雇用状況報告書」で毎年6月1日時点における障害者雇用の状況を報告しなければなりません。
その結果、法定雇用率が未達成で、障害者雇用の取り組みが不十分とみなされた企業には、改善を促す行政指導が入ります。
最初に発出されるのは、管轄のハローワーク所長による「障害者雇入れ計画作成命令」です。その命令を受けた企業は、2年間の雇入れ計画書を作成した上で、計画を実行することが求められます。
それでもなお、計画の遂行を怠っている企業や雇用が進んでいない企業に対しては、さらに企業名の公表を前提とした特別指導が行われる場合もあります。
障害者雇用促進法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
障害者雇用に関する行政指導の流れ

次に、厚生労働省が定める「障害者雇用率達成指導の流れ」に従い、行政指導について段階ごとに詳しく説明します。
参照:厚生労働省「障害者雇用率達成指導の流れ」
1|雇入れ計画作成命令
行政指導の第一段階では、後述する基準を満たしていない企業に対して、ハローワークの所長から「雇入れ計画作成命令」が出されます。計画の始期は翌年の1月で、2年間を想定した計画を立てることが求められます。
計画に記載する内容は、計画の始期と終期、2年間で採用を計画している障害者数などです。
その後、ハローワークが計画の進捗を定期的に確認し、必要に応じて指導や支援を行います。
2|雇入れ計画の適正実施勧告
計画1年目の12月の段階で、計画の実施状況が不十分とみなされた企業には、ハローワークの所長から「雇入れ計画の適正実施勧告」が出されます。この時点で、雇入れ計画通りに遂行していない企業に対し、計画の適正な実施が促されます。
「雇入れ計画の適正実施勧告」や「特別指導」のリスクがあり、早急な対応が必要な場合は、「農園型 障害者雇用支援」を検討するのも有効な手段のひとつです!


3|特別指導
適正実施勧告後も雇用状況の改善が特に遅れており、後述する一定の基準を満たしていない企業は、特別指導の対象となります。雇入れ計画の期間が終了した後、企業名公表を前提として9か月間にわたり集中的に指導が行われる流れです。
なお、特別指導の結果、公表基準を上回った企業は企業名の公表を免れることができます。令和6年1月1日時点での公表基準は以下の通りです。
■令和4年の全国平均実雇用率(2.25%)未満の実雇用率(※)
(法定雇用障害者数が4名以下の企業の場合、当該数が3~4名で雇用障害者数が0名)
※実雇用率:自社の全従業員に占める障害者数の割合
また、公表基準以下の場合でも、以下の公表猶予基準のいずれかを満たす企業は、企業名公表が猶予されます。
■直近の取り組みの状況から、速やかに次のいずれかの状態になることが見込まれる場合
- 実雇用率が令和4年の全国平均実雇用率(2.25%)以上
- 不足数が0名
■次の両方に当てはまる場合
- 特別指導期間終了後の1月1日から1年以内に特例子会社を設立
- 実雇用率が令和4年の全国平均実雇用率(2.25%)以上、または不足数が0名になると判断できる
4|企業名の公表
特別指導の実施後も、最終的に改善がみられないと判断された企業は、厚生労働省のホームページやプレスリリースなどで企業名が公表されます。不足数が特に多い企業の幹部には、厚生労働省から直接指導が入ることもあります。
なお、企業名公表で指導が終わるわけではありません。改善が認められない企業については、再公表される場合もあります。
障害者雇用の行政指導が実施される判断基準

行政指導が行われる具体的な判断基準はあるのでしょうか。厚生労働省では、雇入れ計画作成命令の発出基準を、次のいずれかに該当する場合と定めています。
- 前年の全国平均実雇用率未満の実雇用率、かつ不足数が5名以上
- 不足数が10名以上
- 法定雇用障害者数が3名~4名に対して、雇用障害者数が0名
特別指導は、次のいずれかに該当する企業が対象です。
- 最終年の前年の6月1日現在で、全国平均実雇用率未満の実雇用率
- 不足数が10名以上
厚生労働省の令和5年3月の発表によれば、令和2年4月1日を始期とする雇入れ計画の作成命令を受けた企業は250社に上りました。
そのうち企業名の公表を前提とする特別指導を受けた企業は55社あり、最終的に雇用状況が改善されなかった5社の企業名が公表されました。
出典:
厚生労働省「障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表について~障害者の雇用状況に改善が見られない5社(うち再公表3社)を公表します~」
なお、原則として行政指導に法的拘束力はなく、企業側の協力は任意です。ただし、障害者雇用の状況が是正されないまま企業名の公表に至れば、企業の信用やイメージが失墜する可能性もあります。
障害者雇用がなかなか進まないときの対応策
行政指導の対象となり、さらに社名が公表されるリスクを回避するには、早めに手を打つ必要があります。社内で対応が難しい場合は、国や自治体や公共団体の相談機関のほか、民間の障害者雇用支援サービスを活用するのもひとつの方法です。
公共の相談窓口を活用する
以下の公共の相談窓口では、障害者雇用を支援するサービスが提供されています。支援内容は各機関で異なるため、自社の課題に合わせてご活用ください。
| 相談窓口 | |
|---|---|
| ハローワーク(公共職業安定所) | 全国に約544か所設置。障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓などを提供する。企業は求人の募集や採用に関するアドバイスも受けられる |
| 地域障害者支援センター | 障害者の支援を目的に全国47か所・5支所に設置。職業カウンセラーによる職業評価や職業準備支援に加え、事業主への障害者雇用に関する専門的な助言も行う |
| 障害者就業・生活支援センター | 全国337か所に設置。地域と連携しながら障害者の就業面と生活面を一体的に支援する。事業主からの雇用管理に関する相談にも対応している |
| 独立行政法人・高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) | 障害者の採用や職場適応、休職者の職場復帰などの支援、雇用管理についての相談や助言のほか、障害者雇用納付金制度に関する事業も行う |
民間の支援サービスを受ける
障害者雇用を早期に進めたい場合には、民間の障害者雇用支援サービスの利用が有効です。サービスの利用にはコストが発生する一方で、人材不足やミスマッチ、業務の切り出しの難しさ、定着率の低さといった課題の解決につながるサポートが受けられます。
障害者雇用の民間支援サービスには、次の4種類があります。
雇用コンサルティング
障害者雇用の専門コンサルタントが、採用計画から従業員の定着まで一貫してサポートするサービスです。
企業は、業務の切り出しや職場定着など、障害者雇用に関する課題について、専門的なノウハウを学べるというメリットがあります。障害者雇用の体制を社内で確立したい企業におすすめです。
人材紹介
企業が求める条件やスキルに合致する障害者を、専門のエージェントが探して紹介するサービスです。
企業は、このサービスを通じて自社のみではアプローチできなかった多様な人材と出会えるだけでなく、採用活動にかかる時間や手間を削減できます。採用後のミスマッチのリスクを防ぎ、人材の定着につながりやすい点もメリットです。
BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)
企業が障害者の勤務実績や業務管理などを外部の専門企業に委託するサービスです。
企業は、勤怠管理や業務の切り出し、定着支援などに伴う現場負担を軽減できる点がメリットです。障害者の方にとっては、安心して働ける環境が提供されるという利点があります。
農園型雇用支援
自社で雇用契約を結んだ障害者が、民間サービスの管理する農園で農作業に従事するサービスです。
サポート体制が整った農園での就労は、障害者の方にとってストレスが少なく、安定した定着率を見込めます。企業側も、受け入れ体制の整備や管理業務にかかる負担を軽減しつつ、社会貢献をアピールできます。
まとめ
障害者雇用が進まず、法定雇用率が未達成のまま十分な取り組みが行われない場合、行政指導の対象となり、最終的には企業名の公表に至ります。
障害者雇用に課題や不安を抱えている企業様は、相談機関の支援や民間の障害者雇用支援サービスを積極的に活用し、法定雇用率の達成に取り組むことをおすすめします。
障害者の方が働きやすい環境を提供したい企業様は、ぜひ農園型雇用支援サービスをご活用ください。「めぐるファーム」では、障害者の方が快適かつ安心に働ける環境をご用意しています。
就労する障害者の方は、導入企業と正式な雇用契約を結ぶため、法定雇用率の対象となる仕組みです。2024年12月時点で、めぐるファームには専門スタッフが最大6名常駐し、定着率は95%に及びます。
自社に適した障害者雇用のかたちを模索したい企業様は、ぜひ一度お問い合わせください。
本記コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。