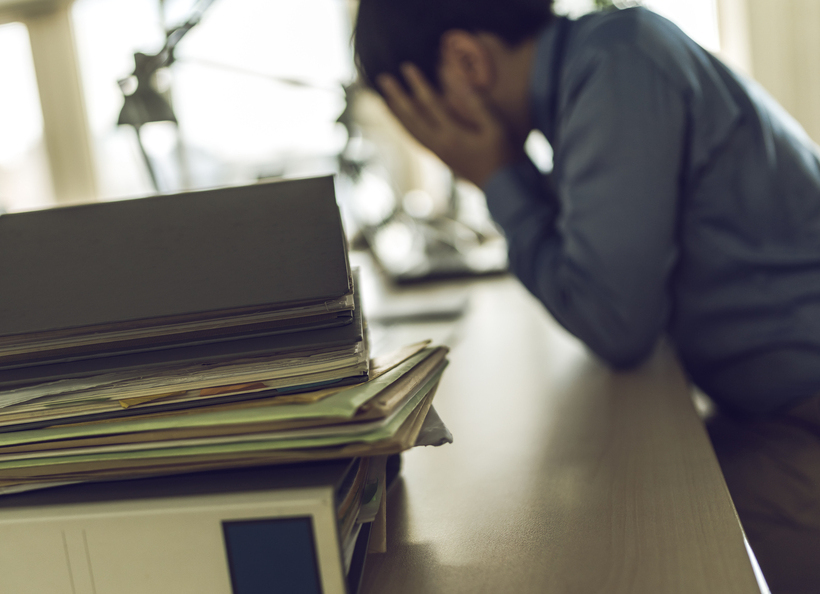障害者雇用を進める上で、制度や計画は整っていても、現場では予想外のトラブルや対応の難しさに直面することが少なくありません。障害者への配慮のつもりが逆効果だったり、周囲の理解が得られなかったりすることもあります。今回は、企業が陥りやすい「障害者雇用のあるある」を8つ紹介します。よくある事例や対策も、ぜひ参考にしてください。
障害者雇用でよくある8つの「あるある」

障害者雇用の現場では、善意のつもりで行った対応が、かえって誤解や、すれ違いを招いてしまうこともあります。ここでは、職場で実際に起こりやすい「あるある」事例を8つ紹介します。
1.業務の切り出しが難しい
障害者に適した仕事を与えようとしても、具体的な業務の切り出しが思うようにいかないことがあります。障害者の特性に応じて、業務内容を調整し、ミスマッチを防ぐ必要があるためです。
業務の切り出しがスムーズにいかないと、周囲の負担が増すとともに「仕事を与えるための仕事」が発生してしまうケースも少なくありません。結果として、雇用後に何を任せるか決めきれないまま、時間だけが経過してしまうこともあります。
2.社内調整がスムーズに進まない
管理職や部門の責任者が障害者雇用の重要性を認識していても、実際に現場で働く社員の理解や協力が得られず、円滑に受け入れが進まないことがあります。
また、本社や管理部など、限られた部署だけで障害者雇用に対応していると、すぐに人員の上限に達してしまい、他の部署への展開が進まないケースもみられます。こうした状況が続くと、法定雇用率を満たすことが困難となり、採用活動にも悪影響をおよぼしかねません。
3.定着率が低い
障害者を採用しても、3か月以内の離職や1年未満での退職が多く、再採用や再調整が必要になることがあります。
2017年度に実施された調査によると、障害者の一般企業における就職後の定着率は、3か月時点で76.5%、就職後1年後で58.4%とされ、長く働き続けてもらう難しさが浮き彫りになりました。
社内体制を整えても、現場のフォローが不十分だったり、業務や人間関係が合わなかったりすることなど、定着率の低下にはさまざまな原因が考えられます。
出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者の就業状況等に関する調査研究」
4.条件に合う障害者社員の採用が難しい
採用方針として身体障害や知的障害の方を希望していても、実際の応募者は精神障害の方が多く、マッチングが難航することがあります。特に、東京都では有効求人倍率が高く、福利厚生の充実した大手企業に人材が集中する傾向があるのです。
また、障害者雇用が難しいと感じる企業の多くは、求人媒体がハローワークのみなど、限定されていることもあります。そもそも応募が集まりにくいため、採用のハードルはさらに上がります。
5.職場での配慮の仕方がわからない
業務を円滑に進めるためには、必要な情報を的確に取り入れられる環境が欠かせません。しかし、障害者に対して配慮しようとするあまり、どの程度の支援が適切か判断に迷うこともあるでしょう。
例えば、通常業務をこなせるにもかかわらず、周囲が気を遣いすぎて業務を軽くするようなケースでは、障害者本人が「自分の能力を正しく評価されていない」と感じてしまうこともあります。
一方、必要な支援が行き届かず、職場のコミュニケーションがうまくいかなくなることもあるようです。コミュニケーションに行き違いが生じると、仕事にも影響をおよぼす可能性があります。
6.仕事に対する評価が難しい
障害者の特性を考慮した上で、どのように業務の成果を評価すべきかに頭を悩ませる企業は少なくありません。配慮を加えた評価であっても、本人側には「正当に評価されていない」と受け取られることもあります。
実際、離職理由として賃金や待遇面への不満が多くあげられており、納得感のある評価基準をどのように構築するかが、継続雇用のポイントとなります。
7.注意をしづらい
障害への配慮を優先するあまり、業務上の指摘や注意ができず、結果的に業務の質が落ちたり、周囲との連携が取りづらくなったりすることがあります。
「指摘したら本人が傷つくかもしれない」、「体調のこともあるから言いにくい」など、障害者への配慮から指導を避ける傾向があるのです。しかし、適切なフィードバックがなければ、企業と本人双方の成長機会を損ねることにもなりかねません。
8.どう関わって良いかわからず対応が遅れてしまう
精神障害や発達障害など、外見から特性が判断できない場合、どう接すれば良いのかわからず、周囲が戸惑ってしまうことがあります。
「この件について聞いてもいいのか」、「どこまで伝えるべきか」と悩んでいるうちに対応が遅れ、両者にストレスがかかってしまう事態になりかねません。誤解や不安が積み重なることで、信頼関係にも影響が出ることがあるため注意が必要です。
障害者雇用におけるトラブル事例

障害者雇用には配慮や理解が求められる一方で、現場ではさまざまなトラブルが起こることもあります。ここでは、実際に起きた障害者雇用におけるトラブル事例を紹介します。
現場で「据え置き」状態になってしまい離職
下肢に障害のある30代の男性は、前職で培ったシステム開発のスキルを活かしたいと考え、大手IT企業の開発職に応募しました。面接時には「未経験の分野でも、上司や同僚がサポートするので安心してください」と説明を受け、入社を決意しました。
しかし、実際の配属先では業務内容の説明がなく、具体的な作業指示もほとんどありません。教育・研修制度の利用も申し出ましたが、「現在は満員なので、空きが出るまで待ってください」と断られ、その後も何の連絡もなかったのです。
入社しても仕事を任せてもらえず、誰にも相談できない状態が続くなかで、徐々に心身の不調をきたし、半年で退職することになりました。
差別的な発言で損害賠償請求に発展
首都圏のスーパーで働いていた知的障害のある男性は、パート従業員の女性指導係から繰り返し差別的な発言を受け、深く傷つきました。男性は精神的に追い詰められ、やむを得ず退職を選ばざるを得なくなったのです。その後、男性は精神的苦痛を理由に、勤務先の企業と指導係の女性を訴えました。
裁判では、女性による発言が不適切であると認められ、損害賠償の支払いが命じられました。さらに、控訴審では和解が成立し、「障害の特性に即した業務や職場環境を提供し、関係者に対する適切な指導方法や対応を教育する必要があったが、それが不十分だった」と明記された和解条項が文書に盛り込まれました。
障害者雇用のよくあるトラブルを回避するポイント

障害者雇用におけるトラブルを未然に防ぐには、日常的な配慮と社内全体の理解促進、そして外部支援の活用が重要です。ここでは、障害者雇用で起こりがちなトラブルを回避するためのポイントを解説します。
常に心身の状態を把握する
問題が深刻化する前に、定期的な面談の機会を設け、障害者の心身の状態を丁寧に把握しておくことが大切です。障害者がもつ特性から業務に支障が出たり、不安定な精神状態に陥ったりすることもあるかもしれません。
そのため、よりきめ細やかに不安や悩みを聞き取る姿勢が求められます。ただし、会社側として対応が困難なことについては、面談時に率直に伝えることも重要です。
必要に応じて、通院や服薬について本人と相談し、配慮できる体制を整えましょう。体調に変化があった際も柔軟な対応がとれる体制をつくっておくことがポイントです。
社内の障害への理解を促す
障害への理解を深めるには、まず企業の代表責任者が障害者雇用の方針や意義を明示し、社内全体へ周知することが重要です。
その上で、定期的な勉強会や情報共有を通じて、障害特性に関する正しい知識や配慮方法などを社内全体に浸透させましょう。理解が進むことで、現場での不安やトラブルを減らすことができます。
支援機関や民間サービスを利用する
社内での対応が難しく、同じような問題が繰り返される場合は、外部支援機関の活用を検討してはいかがでしょうか。民間企業の中には、障害者雇用に特化したコンサルティングや定着サポートなどを行っているところもあります。専門知識をもつ第三者の力を借りることで、障害者雇用をスムーズに進められます。
まとめ
障害者雇用を成功させるには、制度面の整備だけでなく、現場で働く社員の理解と協力が不可欠です。トラブルを未然に防ぎ、障害者に長く働き続けてもらうためには、継続的な取り組みと柔軟な対応力も求められます。
障害者雇用で外部支援を検討中であれば、めぐるファームがおすすめです。めぐるファームはNEXT ONEが展開する「農園型障害者雇用支援事業」のひとつで、障害者と雇用主の両者がしっかりと向き合える環境を提供します。
障害者雇用を円滑に進めたい方は、めぐるファームをぜひご検討ください。
本記コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。