
自社が障害者雇用を義務付けられているものの、法定雇用率を達成できず悩んではいませんか。法定雇用率を下回ってしまったら、どのようなことが起こるのでしょうか。
今回は、障害者雇用に関する納付金やペナルティ、またそうならないための対処法について解説します。
障害者雇用率未達成の場合には罰金がある?

常時雇用する労働者が100人を超える企業には、障害者法定雇用率の達成が求められ、未達成の企業は納付金を支払う必要があります。納付金は罰金ではないため、支払ったからといって障害者雇用の義務がなくなるわけではありません。
ここでは、納付金とは何かについて解説します。
障害者雇用納付金については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
なぜ納付金を支払うのか
「障害者雇用促進法(正式法令名 : 障害者の雇用の促進等に関する法律)」では、障害者雇用納付金制度を定めています。この制度は、障害者法定雇用率が未達成の企業から納付金を徴収し、達成した企業に対して、集められた納付金から障害者雇用調整金や報奨金などを支給する仕組みです。
障害者を雇用するには、バリアフリー対応のための設備の改修、障害者をサポートする人員の配置などの環境整備が必要です。障害者雇用納付金制度は、障害者を雇用する企業の経済的負担の調整として設けられています。
納付金額について
障害者雇用納付金制度の対象企業の障害者雇用率が法定雇用率を下回った場合、障害者雇用納付金の支払いが必要です。
実際の雇用率と法定雇用率との比較は、月ごとに行います。毎月、法定雇用率を下回らずに障害者を雇用している場合は、納付金を納める必要はありません。
しかし、ひと月でも法定雇用率を下回る月があるときは、以下の計算式により納付金を算出して納める必要があります。納付金の額は、不足している人数1名につき月額5万円です。
<計算式>
納付金の額=(法定雇用障害者数-常用障害者数)の各月の合計×5万円
「農園型 障害者雇用支援」を導入することで、障害者の方を雇用でき、「障害者雇用納付金」を避けることができます。一度検討してみませんか?


障害者雇用納付金の支払いに関するルール
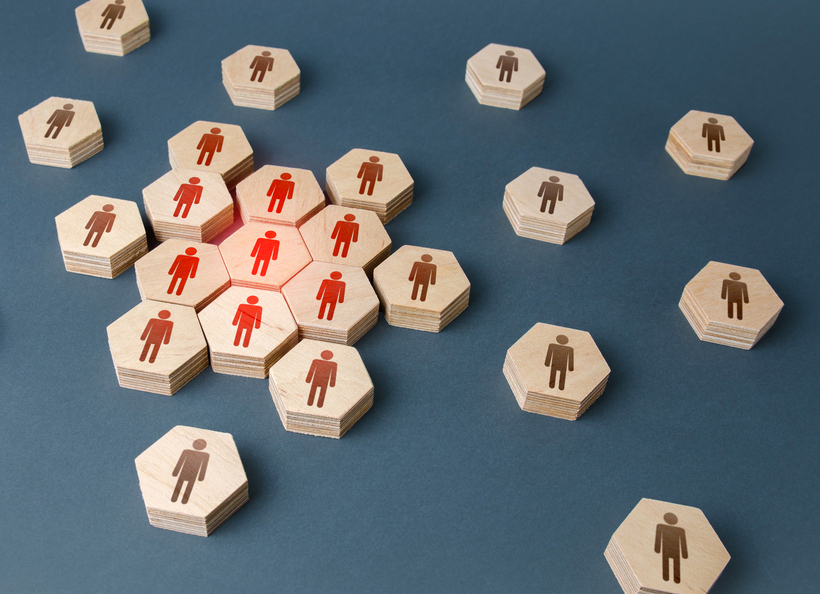
障害者雇用納付金の支払いについて解説します。
納付方法
障害者雇用納付金は、事前に交付された納付書を用いて納付します。納付方法は、金融機関窓口とペイジー(インターネットバンキング)の2つです。
金融機関窓口で納付する際は、交付された納付書を提出して支払います。ATMなどを利用した振り込みによる納付には対応していません。
ペイジー(インターネットバンキング)による納付は、納付金取扱金融機関から行います。対応している銀行は、JEED(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)が公表している「障害者雇用納付金取扱機関及び電子納付(ペイジー)対応金融機関」から確認できます。
納付のタイミングと期限
障害者雇用納付金の納付のタイミングは、例年4月1日から5月15日までです(※)。
納付金額が100万円以上になるときは、延納を申請できます。延納を申請した場合は年3回までの分割納付となります。それぞれの納付期限は、第1期が5月15日まで、第2期が7月31日まで、第3期が12月1日までです(※)。
延納の申請を行わない場合は、納付金額が100万円以上であっても、毎年5月15日が納付期限です。納付金が発生する場合は、納付のタイミングに注意しましょう。
※土・日・祝の関係上、スケジュールが前後する場合があります。
延滞したときの対応
障害者雇用納付金の期限を過ぎてしまったときは、速やかに納付しましょう。
納付書に印字された期限を過ぎていても金融機関の窓口で納付できます。期限の指摘を受けた場合は、使用できる旨を伝えましょう。
ペイジーの場合は、収納機関番号(48001)と納付番号(13桁)、確認番号(6桁)、納付区分(100)がわかれば納付できます。
納付書記載の確認番号の有効期限が過ぎている場合は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の納付金部管理課収納係(TEL:043-297-9651)に電話で確認します。
法定雇用率が未達成だった場合の3つのペナルティ

障害者の雇用割合が法定雇用率に達しなかった場合、3つのペナルティが発生します。
障害者雇用納付金の納付
常時雇用する従業員が100人超の企業は、ここまで紹介したように、法定雇用率に達しないときは、障害者雇用納付金を支払う必要があります。判定に用いられる常用労働者は、週の所定労働時間が20時間以上で、1年超雇用されている従業員のことです。
ハローワークによる行政指導
障害者の法定雇用率に満たない場合、ハローワークからの行政指導の対象になります。
行政指導となった場合、障害者の雇い入れについて2年間の計画書を作成して提出しなければなりません。計画書の提出後は、計画に沿って障害者雇用の取り組みが行われているか確認があります。
計画通りに行われていないときは、適正に実施するよう是正勧告が行われます。全国平均よりも実雇用率が低い場合や障害者雇用の不足人数が10人以上になる場合は、特別指導の対象です。
企業名の公表
9か月の特別指導を受けても法定雇用率を達成できない場合は、「障害者雇用促進法」第47条により、企業名や代表者名などが公表されます。
報道関係者向けに厚生労働省がプレスリリースを出したことで、過去にはニュースで取り上げられた事例もあります。
企業名が公表されると、企業イメージが悪化することになりかねません。勧告を受けても法を順守しなかった企業として、顧客や取引先からの信用に影響を与える可能性があります。信用の低下は、従業員のモチベーションにも悪影響を及ぼします。
障害者雇用率未達成のペナルティを回避するための方法
厚生労働省の障害者雇用状況調査によると、令和6年度の法定雇用率未達成企業は63,364社でした。過半数は不足人数0.5人~1人で、全体の64.1%を占めます。
障害者を1人も雇用していない企業は、36,485社でした。法定雇用率未達成企業の57.6%を占めています。
法定雇用率を達成できていない企業も多いとはいえ、義務が果たせていない場合はペナルティが発生します。ペナルティ回避のためには、障害者雇用を積極的に進めていく必要があるでしょう。
ここでは、企業が障害者雇用を進める方法を紹介します。
出典:厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」
1.障害者雇用に対する社内理解を深める
障害者雇用促進法には、障害者も社会の一員として能力を発揮できるようにするという目的があります。労働によって実現するには、事業主の協力と周囲の理解が必要です。
経営層のほか、障害者雇用に関わる人事部や配属先において、障害者雇用の意義や理念について理解を深めていくことが重要です。研修や勉強会などを通じて、社内理解を促します。
2.現状を把握し、障害者の雇用計画を立てる
法定雇用率と実雇用率を比較し、不足している場合は必要な雇用人数を算出します。
現状の計画で達成が難しい場合は、新規業務の創出や切り出し、配属先の選定や受け入れ体制の整備、採用手法の見直しなどを検討します。
3.障害者雇用における課題点を整理する
雇用している障害者の自社の定着率や離職率を把握し、定着率に問題がある場合はどのような課題があるか整理します。定着率が良くない原因は企業によってさまざまです。
例えば、障害者への合理的配慮ができていない、社内理解ができておらず障害者への不適切な言動がある、マネジメントが適切でないなどがあります。
障害者雇用の定着率についてはこちらで詳しく解説しています。
4.障害者雇用に関する公的相談窓口や助成金を活用する
障害者雇用を進めるには、関連機関との連携が重要です。障害者雇用をサポートする公的機関には、ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターがあります。
ハローワーク(全国544か所)は、就労支援サービスを幅広く提供している機関です。障害者雇用について何をすれば良いかわからないときの相談先に適しています。
地域障害者職業センター(全国47か所+5支所)は、障害者雇用の促進を専門とした機関です。障害者雇用についての計画書の作成など、実践的なサポートを受けたい場合に向いています。
障害者就業・生活支援センター(全国388か所)は、障害者を就業と生活の両面からサポートする機関です。生活面での支援が必要な障害者の雇用を進める企業の相談先に適しています。
なお、障害者雇用を進める際は、企業にさまざまな経済的負担が生じます。国は、障害者雇用に取り組む企業に対して、複数の助成金制度を設けています。助成金を活用することで、コストを抑えて障害者雇用を進めることが可能です。
障害者雇用における助成金について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
5.民間の障害者雇用支援サービスを検討する
公的機関のほか、民間でも障害者雇用の支援は行われています。
民間サービスを利用するメリットは、企業のニーズに合わせた支援を受けられる点です。企業の規模や配置に合わせた提案や業種に合った業務の切り出しの提案などを期待できます。
障害者の在宅勤務の実現をサポートするサービスや農園を利用した障害者向けの業務を提供するサービスなどが展開されています。
農業型障害者雇用については、こちらの記事で詳しく紹介しています。
まとめ
障害者法定雇用率の未達成の企業に罰金はありません。しかし、障害者雇用促進法に基づき、不足している人数分の納付金を負担する必要があります。自社の取り組みだけで障害者雇用が進まない場合は、公的機関や民間のサポートも検討しましょう。
農園型雇用支援なら、「めぐるファーム」の利用をご検討ください。
めぐるファームは、障害者の就労場所や日々の業務管理、サポートを提供しています。障害者の雇用や給与の支払い、社会保険関係は利用者である企業側が行う仕組みです。企業は正式に障害者を雇用する立場になるため、法定雇用率のカウント対象になります。
本記コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。


























