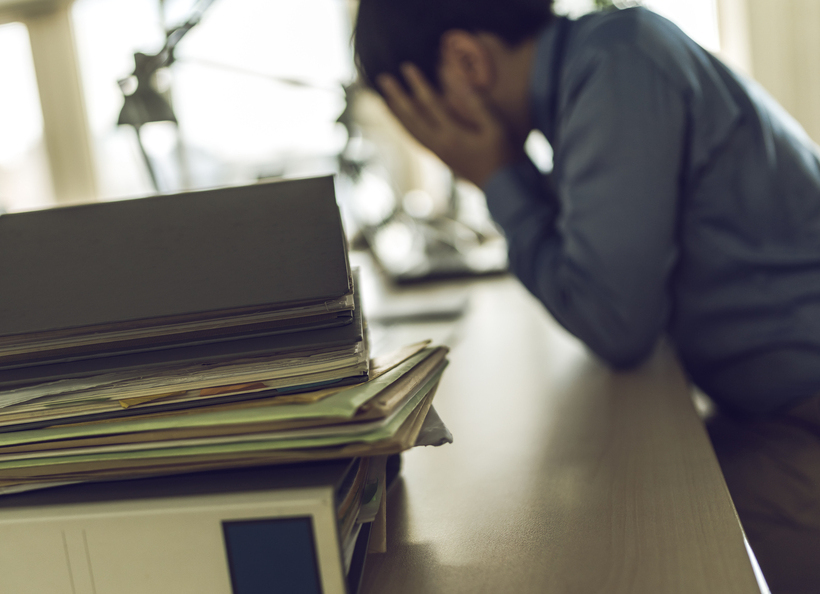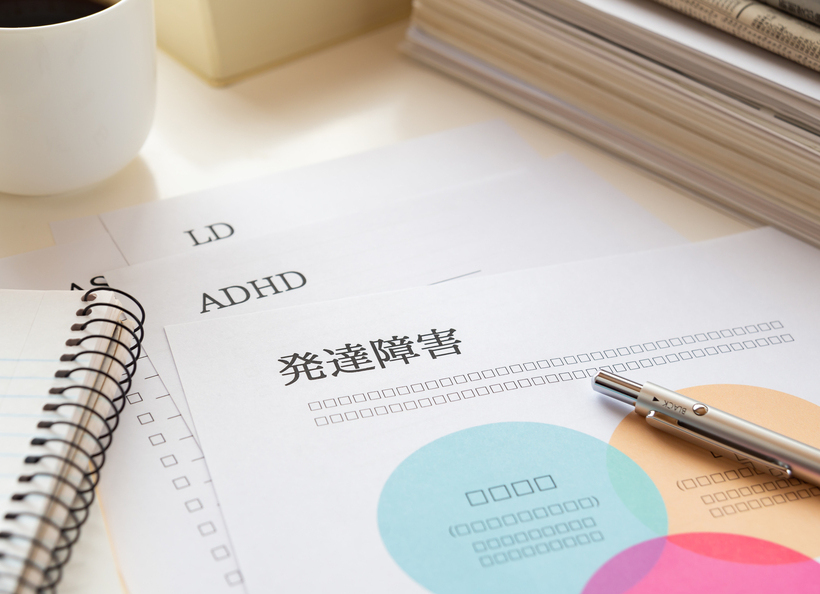
多くの企業では、障害のある方が職場で能力を発揮できるよう取り組みを進めています。しかし、「どのようにして発達障害者の雇用を進めればよいのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。
発達障害にはさまざまな特性があるため、雇用する側にも正しい理解と柔軟な対応が求められます。
今回は、発達障害者の雇用に関する法的なルールや制度について解説しながら、雇用を進める際のポイントについて紹介します。
障害者雇用制度の「発達障害者」に関するルール

発達障害者の雇用については、「障害者雇用促進法(正式法令名 : 障害者の雇用の促進等に関する法律)」や「発達障害者支援法」など、いくつかの法的枠組みの中で定義されています。発達障害は身体に表れにくいため、制度の内容を正しく理解していないと、支援が行き届かないケースも少なくありません。
まずは、発達障害者がどのように法制度の対象となるのか、障害者の雇用数に関するルールについて押さえておきましょう。
対象者
発達障害とは、先天的または早期に発現する脳の機能障害のことであり、「自閉症スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害(ASD)」、「アスペルガー症候群」、「学習障害(LD)」「注意欠陥多動性障害(ADHD)」などが代表例です。発達障害者支援法では、これらを総称して「発達障害」と定義しています。
発達障害者が障害者雇用の対象となるには、主に「精神障害者保健福祉手帳」を取得していることが基本条件です。精神障害者保健福祉手帳を取得することで、精神障害者として法的な支援の対象となり、企業の法定雇用率にもカウントされます。
また、知的障害を併せ持っている場合には「療育手帳」を取得することもあり、その場合は知的障害者としての支援や雇用対象になります。
出典:文部科学省「発達障害者支援法」
カウント方法
一定規模以上の企業は、障害者を法定雇用率以上で雇用することが義務づけられています。発達障害者が「精神障害者保健福祉手帳」を所持している場合、その雇用数は「精神障害者」としてカウントされます。
下表は、障害の区分と週の所定労働時間に応じたカウント数です。
| 週所定労働時間30時間以上 | 週所定労働時間20~30時間未満 | 週所定労働時間10~20時間未満 | |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 1人 | 0.5人 | ― |
| 重度身体障害者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 知的障害者 | 1人 | 0.5人 | ― |
| 重度知的障害者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 精神障害者 | 1人 | 1人 | 0.5人 |
出典:厚生労働省「障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~」
雇用すべき障害者数について、詳しくはこちらをご覧ください。
発達障害者の雇用状況

障害者の雇用は年々増加傾向にあります。厚生労働省が公表した「令和5年度障害者雇用実態調査」によれば、全国6,406社の回答事業所において、令和5年6月時点で雇用されている発達障害者は推計9万1,000人でした。
ここでは、厚生労働省の調査結果をもとに、発達障害者の実際の雇用実態について解説します。
平均労働時間
厚生労働省の調査結果によると、発達障害者の週の平均労働時間は「30時間以上」が全体の60.7%を占めています。つまり、一般的なフルタイム勤務に近い形で働いている方が多いことを示しています。
一方で、20時間以上30時間未満の就労が約30%、20時間未満の就労も一定数存在しており、短時間勤務を選択している方も少なくありません。
出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」
平均月額賃金
発達障害者の月額平均賃金は全体で13万円(所定内給与は12万8,000円)と報告されています。週30時間以上勤務している場合は平均15万5,000円と比較的高く、労働時間に比例して賃金水準も上昇する傾向があります。
20時間以上30時間未満のケースでは10万7,000円、10時間以上20時間未満では6万6,000円、10時間未満では2万1,000円です。
支払い方法としては、月給制が52.3%と最も多く、次いで時給制が44.2%、日給制は1.1%です。つまり、安定した収入を得ることを目的とし、企業が正規雇用または長期雇用を前提に採用しているケースが多いことがわかります。
出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」
障害の種類・等級
発達障害者の多くは、「精神障害者保健福祉手帳」を取得して雇用されています。その中で最も多い等級は「3級」で、全体の41.1%です。次いで「2級」が23.6%という結果になっており、比較的軽度~中等度の障害を持つ方が多く働いていることがわかります。
障害の種類としては、「自閉症」、「アスペルガー症候群」などの広汎性発達障害が最も多く、全体の69.1%を占めています。次に多いのが「注意欠陥多動性障害(ADHD)」で15.2%でした。
出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」
発達障害者の雇用を進める際のポイント

発達障害者の雇用を推進するためには、法令を遵守するだけでなく、実際の職場における配慮や対応が重要です。発達障害は一人ひとり特性が異なり、職場での困りごとも多様です。そのため、一般的なマニュアル対応ではなく、柔軟かつ個別対応が求められます。
ここでは、社内で取り組みたい対応や支援のあり方について解説します。
社内の発達障害に対する理解を深める
発達障害者を受け入れる際にまず必要なのは、社員全体が障害特性に対する理解を深めることです。
発達障害は目に見えない特性であり、理解が不足していると「なぜできないのか」と誤解を生む原因にもなります。企業には「合理的配慮」の提供が求められており、これは努力義務ではなく、法律に基づく対応です。
合理的配慮とは、障害のある従業員が他の従業員と同等に働けるよう、過度な負担をかけない範囲で環境の整備や業務を調整することです。
例えば、業務の手順を文章化したり、指示を口頭ではなく視覚的に伝えたりといった工夫が該当します。まずは社内で研修を実施するなどして、全体の意識改革を図ることが大切です。
個別の支援を行う
発達障害は個人差が大きいため、画一的な支援ではうまく機能しないケースも多くみられます。そのため、本人のニーズや特性に合った個別の対応が必要です。
例えば、業務の目的や手順を個別に伝えることで、各々が役割を理解し、混乱や不安を軽減できます。
また、視覚的なマニュアルの活用や、チェックリストによる進捗管理なども効果的です。加えて、コミュニケーションスタイルにも配慮が求められます。一度に複数の指示を与えるのではなく、ひとつずつ簡潔に伝えることが望ましいでしょう。
さらに、音や光など感覚過敏に対する配慮も重要です。騒がしい環境では集中できない方も多いため、静かな作業スペースの確保や照明の調整など、職場環境も整備しましょう。
特性に応じた職種・業務を割り当てる
発達障害と一口に言っても、その特性はさまざまです。本人の強みを活かすためには、特性に合った業務の割り当てが求められます。以下はその例です。
- ASD(自閉スペクトラム症)の傾向がある方:ルーティン化された作業や、一人で黙々と取り組める仕事
- ADHD(注意欠如多動症)の傾向がある方:興味関心が高い分野で、多少の自由度があり、クリエイティブな業務
- SLD(限局性学習症)の傾向がある方:読み書きや計算を必要としない、実作業中心の仕事や身体を動かす業務
特性に応じた適材適所の配置により、双方にとってストレスの少ない就労環境が実現できます。
障害者雇用支援も検討する
企業が発達障害者の雇用を進める上で、外部支援の活用も大きな助けになります。
- ハローワーク:専門の相談員による職業相談や紹介を受けられる
- 障害者トライアル雇用事業:一定期間(原則3か月)試行的に雇用でき、雇用継続の判断材料とする制度で、助成金も支給される
- 精神・発達障害者雇用サポーター:発達障害者の雇用を支援する専門職。雇用前後のアドバイス、業務環境への配慮方法などについて企業に対する助言を提供する
- ジョブコーチ支援:職場に専門支援員(ジョブコーチ)を派遣し、本人が業務に慣れるまで定着を支援する。業務指導や人間関係の橋渡しも担う
近年、民間のサポートを活用する方法として「農園型就労支援」も注目されています。農園型就労支援は、企業が農園を借り、雇用した障害者を就労させる仕組みです。農園の管理や障害者の業務サポートは運営会社に任せられるため、障害者雇用に関する知識やリソースがない企業でも、スムーズに障害者雇用を進められます。
農園型就労支援については、こちらで詳しく解説しています。
まとめ
発達障害者の雇用を進めるためには、法律や制度を正しく理解することが大切です。また、発達障害には多様な特性があり、働く上での困難も人それぞれ異なります。そのため、個別の特性に応じた配慮と環境整備も欠かせません。
自社に障害者雇用に関する知識やリソースがない場合は、外部の公的支援制度や民間支援を活用するのも有効です。農園型雇用支援の「めぐるファーム」では、障害者が快適に働ける屋外ハウスを運営しています。
社会福祉士や看護師といった国家資格を持つ専門スタッフが常駐し、作業のサポートだけでなく、企業と障害者社員の間に立ったコミュニケーション支援も提供しています。障害者雇用をスムーズに進めたい企業は、ぜひご検討ください。
本記コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。