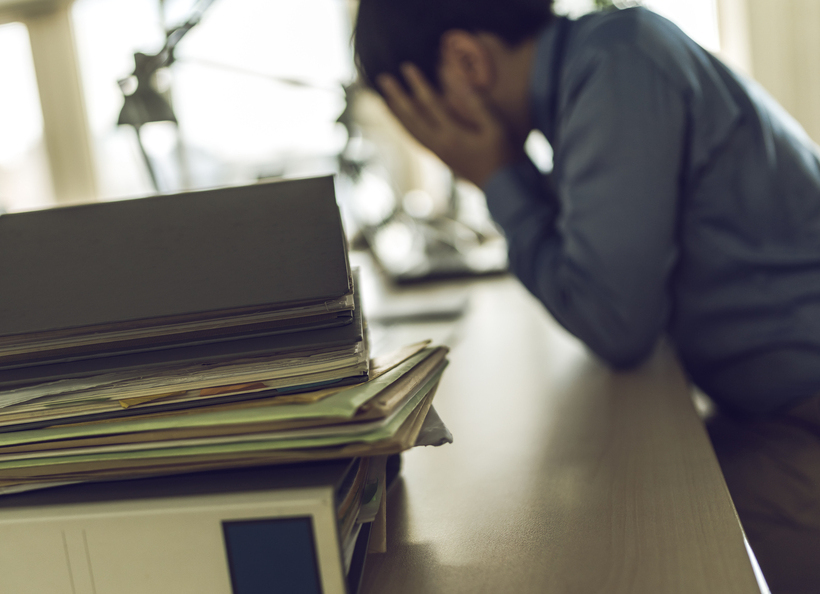日本には企業に対して一定の障害者雇用を義務づける法律があり、それに基づいて設けられているのが「障害者雇用枠」です。しかし、障害者雇用枠とは具体的に何を意味するのか、一般雇用枠とはどう違うのか、採用する側・採用される側ともに理解が不十分なケースも少なくありません。
今回は、障害者雇用枠の概要や一般雇用との違い、採用に悩んだときの解決策について解説します。障害者の就労をめぐる環境を正しく理解し、より良い職場づくりにつなげましょう。
障害者雇用枠とは?
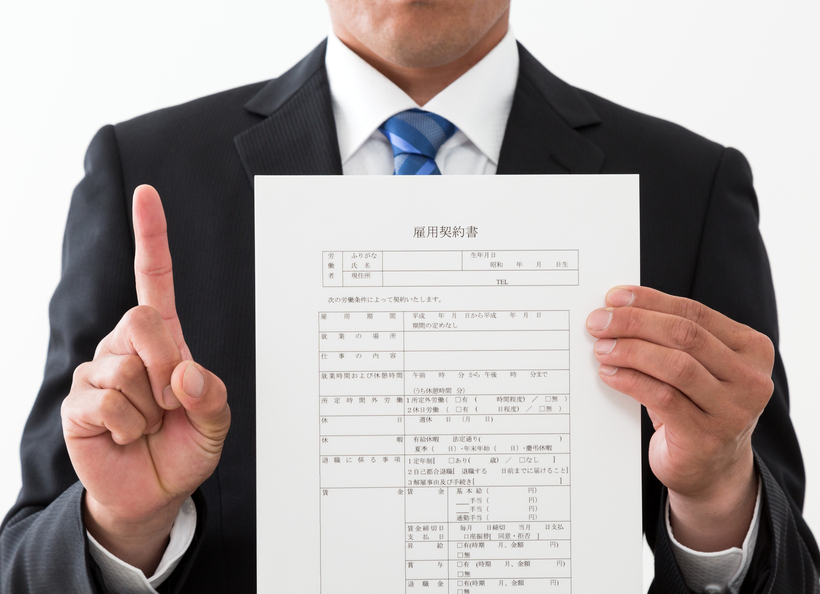
「障害者雇用枠」とは、障害者手帳(身体・知的・精神)を所持している方を対象に、企業が設けている特別な採用枠のことを指します。「障害者雇用促進法(正式法令名 :障害者の雇用の促進等に関する法律)」に基づき、一定規模以上の企業に対して、障害者を法定雇用率以上で雇用することが義務づけられています。
例えば、2025年時点では民間企業の法定雇用率が2.5%であり、従業員(常用労働者)が40人以上いる場合は障害者を1人以上雇用しなければなりません。
法定雇用率を満たすため、多くの企業が一般の採用枠とは別に「障害者雇用枠」を設定し、配慮ある職場環境の整備とともに、障害者の就労をサポートしています。障害者雇用枠では、障害特性や必要な配慮事項が事前に共有されるため、入社後も働きやすい環境が整いやすいのが特徴です。
なお、法定雇用率の詳細については後ほど詳しく説明します。
一般雇用枠との違い
障害者雇用枠と一般雇用枠の大きな違いは、採用の際に「障害があることを前提として配慮されるかどうか」です。
どちらも採用試験を経て入社する点は同じですが、障害者雇用枠では、障害の特性や必要な支援をあらかじめ企業に伝えることで、勤務形態や仕事内容、設備面などにおいて適切な配慮を受けやすくなります。
一方で、障害者手帳を持っていても、あえて一般求人に応募して仕事に就く方もいます。
しかし、厚生労働省の調査では、1年後の職場定着率は障害者雇用枠のほうが一般雇用よりも高い傾向があり、安定して働き続けたい方にとっては障害者雇用枠が有利といえるでしょう。
また、障害者雇用枠では募集職種が限定的になりやすく、給与水準も低くなる傾向があります。
令和5年に実施された厚生労働省の「障害者雇用実態調査」では、身体障害者の月額平均賃金が23万5,000円、知的障害者が13万7,000円、精神障害者が14万9,000円となっており、同年の全国平均賃金31万8300円と比較して差があることがわかります。
出典:
厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」
厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概要」
障害者雇用枠の雇用に関するルール

企業側は、障害者を一定割合で雇用する義務がある一方で、求職者側も特定の条件を満たす必要があります。ここでは、障害者雇用枠に関連するルールについて解説します。
法定雇用率
日本では、障害のある方が社会で自立し、継続的に働く機会を得られるように「障害者雇用率制度」が設けられています。障害者雇用率制度により、一定規模以上の事業主には、従業員の総数に対して一定割合の障害者を雇用する義務があります。この割合が「法定雇用率」です。
2025年時点では民間企業の法定雇用率は 2.5% に設定されており、常用労働者が40人以上いる企業では、1人以上の障害者を雇用しなければなりません。2026年7月からはこの法定雇用率が 2.7% に引き上げられる予定です。
法定雇用率について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
対象者・条件
障害者雇用枠での就労を希望するには、一定の要件を満たしている必要があります。その基本となるのが「障害者手帳」です。具体的には、以下のいずれかの手帳を持っていることが条件となります。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳(知的障害者を対象) ※自治体により「愛の手帳」、「みどりの手帳」など名称が異なることもある
- 精神障害者保健福祉手帳
これらの手帳は、医師の診断書などに基づいて、地方自治体から障害の認定を受けた方に交付されます。したがって、障害があると自覚していても、手帳を持っていない場合は原則として障害者雇用枠の対象にはなりません。
また、障害の種類もさまざまであり、以下のような分類が存在します。
<障害者雇用の対象となる主な障害の種類と例>
| 障害の種類 | 主な概要 | 具体例 |
|---|---|---|
| 身体障害 | 身体の機能に制限がある障害 | 視覚障害、聴覚障害、上肢・下肢の欠損、内部障害(心臓・腎臓など) |
| 知的障害 | 知的発達の遅れにより日常生活や就労に支障がある | ダウン症、脳性麻痺による知的遅滞など |
| 精神障害 | 精神疾患により長期的に社会生活が困難になる | 統合失調症、うつ病、発達障害(ADHD、自閉スペクトラム症など) |
障害者雇用枠の労働に関する3つのルール
障害のある方が職場で安心して長く働けるようにするため、障害者雇用枠には働き方や処遇について一定のルールがあります。ここでは、障害者雇用枠におけるルールについて解説します。
雇用形態
障害者の雇用には、正社員、嘱託社員、契約社員、パート、アルバイトなどさまざまな形態があります。このような雇用形態は、企業の業務内容や体制、本人の希望、能力に応じて決定されるのが一般的です。
例えば、短時間勤務を希望する方には、パートタイムでの就労を提案することがありますが、これはあくまで本人との合意に基づくものであり、一方的に決定してはいけません。障害があるからといって最初から正社員を排除するような扱いは、「障害者差別解消法(正式法令名 : 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」により明確に禁じられています。
また、どの雇用形態であっても、週20時間以上(重度障害者については10時間以上)働いていれば、法定雇用率の対象となります。ただし、週所定労働時間によって算定の仕方が異なるため、就業時間とのバランスも考慮しましょう。
就業時間
障害者の就業時間については、切り出した業務内容や、本人の健康状態・生活リズム・希望などを踏まえた上で各企業が決定します。長時間勤務が難しい場合は、短時間勤務や時差出勤など柔軟な働き方を提案することが重要です。
また、法定雇用率の算定においては、「週所定労働時間」と「障害の区分」に応じてカウントされる人数が異なります。
| 障害の区分 | 週所定労働時間30時間以上 | 週所定労働時間20~30時間未満 | 週所定労働時間10~20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 1人 | 0.5人 | ― |
| 重度身体障害者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 知的障害者 | 1人 | 0.5人 | ― |
| 重度知的障害者 | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 精神障害者 | 1人 | 1人 | 0.5人 |
賃金
障害者の賃金は「障害の有無」ではなく、「業務の内容」、「職務遂行能力」、「経験・在籍年数」などに基づいて公平に決定しましょう。同一の仕事をしている場合は、障害のある方もない方も同じ賃金が支払われるのが原則です。
しかし、障害の程度や特性により業務内容が限定される場合や、習得に時間がかかる場合などは、他の従業員よりも低い給与から始めることも、合理的な範囲であれば許容されます。
また、障害者であっても最低賃金法は適用されます。特例的に「減額特例許可制度」により最低賃金を下回ることが認められるケースもありますが、それには都道府県労働局長の許可が必要です。
基本的には、障害者であることを理由に、法律で定められた最低賃金を下回る賃金を設定してはならず、その点においても企業の適正な運用が強く求められます。
障害者雇用枠での採用に悩んだときの解決策
障害者雇用を進めるにあたって、制度は理解していても「どうやって採用すればいいのかわからない」、「職場環境をどう整えればいいのか不安」といった悩みを抱える企業は少なくありません。
特に初めて障害者を雇用する企業にとっては、採用から定着までを一貫してサポートできる仕組みを見つけることが重要です。ここでは、採用に悩んだときの解決策を紹介します。
障害者雇用について各種窓口に相談する
障害者雇用を検討する際、法制度や実務に不安を感じた場合は、専門機関への相談がおすすめです。
【全国のハローワーク】
障害者雇用に関する基本的な制度説明や、求人の出し方などについてアドバイスを受けられます。初めて障害者を採用する企業にとっては、何から始めればよいかわからないという声も多いため、最初の窓口として適しています。
【地域障害者職業センター】
より実践的な支援を求める場合におすすめの相談先です。障害特性に応じた職務設計や、職場適応に関する助言を受けられます。
【障害者就業・生活支援センター】
障害者本人の生活面も含めたサポートを提供しており、雇用後の定着支援に課題を感じている企業におすすめの相談先です。
障害者雇用にまつわる助成金を活用する
障害者を雇用するにあたっては、業務の切り出しや職場環境の整備、通勤支援など、通常以上に配慮や対応が求められます。これらのコストや負担を軽減するため、国は「障害者雇用促進法(正式法令名 : 障害者の雇用の促進等に関する法律)」に基づき、企業向けにさまざまな助成金制度を設けています。
- 特定求職者雇用開発助成金:障害者を新たに雇用した企業に対し、一定の条件下で支給される助成金
- キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース):有期雇用契約で雇用した障害者を正社員へ転換した場合に支給される助成金
- トライアル雇用助成金:職務適性などを見極めるために、試行雇用する企業に支給される助成金
これらの助成金制度を活用すれば、障害者にとって働きやすい環境を整えつつ、企業側の負担も軽減できます。
障害者雇用にまつわる助成金について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
障害者雇用の民間支援サービスを利用する
障害者雇用を自社で進めるのが難しい場合は、民間の支援サービスを活用するのも有効な手段です。
民間の支援サービスを活用することで、障害者人材の確保やマッチング、職場定着の支援など、雇用プロセス全体を専門的にフォローしてくれます。
障害者雇用の民間支援サービスには、次のようなものがあります。
- 雇用コンサルティング:企業の状況に応じた採用計画の立案や職務設計の支援を受けられる
- 人材紹介サービス:障害者の特性や希望にマッチした人材を紹介してもらえ、ミスマッチによる早期離職のリスクを下げることが可能
- BPO:障害者の勤務実績や業務内容のフォローといった管理業務を委託できる
- 農園型雇用支援:企業が自社で雇用契約を結んだ障害者が、民間サービスが管理・運営する農園で農作業をする形態
農園型雇用支援については、こちらで詳しく解説しています。
まとめ
障害者雇用枠は、企業が障害者を雇用する際に設ける特別な採用枠です。適切な労働環境や支援体制を整えることで、障害者が安心して長く働ける職場が実現できます。
障害者雇用に不安を感じる企業は、農園型雇用支援の「めぐるファーム」活用もご検討ください。めぐるファームでは、企業が正式に雇用契約を結んだ障害者が、NEXT ONEの農園で働く形式を採用しています。
日々の業務管理やサポートはNEXT ONEが担当するため、企業側の負担を大きく軽減しながらも、法定雇用率の対象としてカウントされます。障害者雇用を無理なく進めるためにも、ぜひご相談ください。
本記コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。