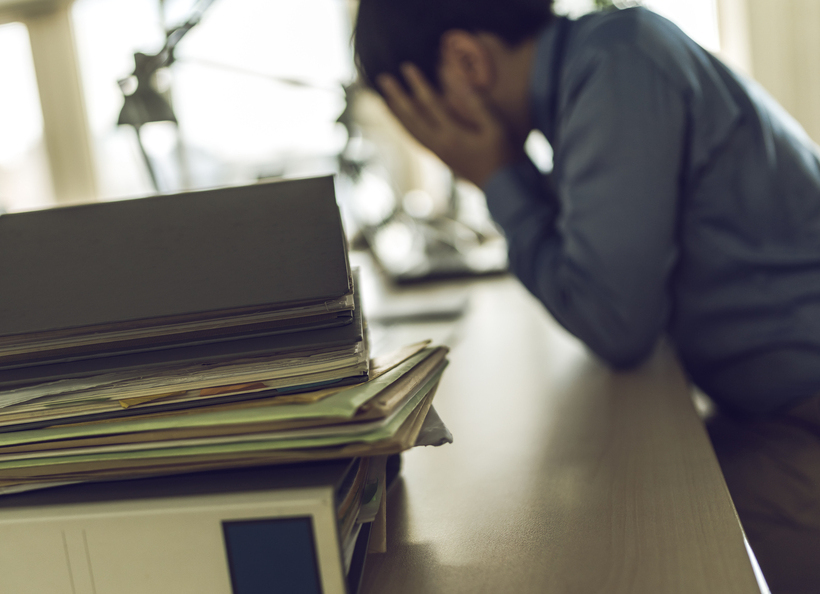身体障害者手帳は、障害のある方が日常生活や就労において必要な支援を受ける上で欠かせないものです。しかし、手帳には「等級」という分類があり、これが支援内容や雇用のカウント方法に大きく影響します。
障害者雇用に関わる方は、等級について正しく理解しておきましょう。今回は、身体障害者手帳の等級の意味や分類、雇用のルールなどをわかりやすく解説します。
身体障害者手帳の「等級」とは?

身体障害者手帳には、障害の程度によって「等級」が設けられています。この等級は、障害が日常生活や社会参加にどれほど影響を与えているかを示す目安となり、受けられる福祉サービスの内容や、企業での障害者雇用数にカウントされるかどうかにも関わります。
つまり、等級の違いによって、支援の範囲や企業の対応も変わるということです。ここでは、身体障害者手帳とは何か、等級がどのように分類されているのかを解説します。
そもそも身体障害者手帳とは
身体障害者手帳とは、視覚や聴覚、肢体不自由、心臓や腎臓など内臓機能の障害を持つ方に対して、市区町村が交付する公的な証明書です。
障害者手帳には、「身体障害者手帳」を含めて3種類あります。
・療育手帳:知的障害のある方が対象 ※自治体により「愛の手帳」、「みどりの手帳」など名称が異なることもある
・精神障害者保健福祉手帳:精神障害のある方が対象
身体障害者手帳を持つことで、障害者総合支援法に基づくサービス、医療費助成、交通機関の割引など、日常生活を支えるさまざまな支援を受けられます。
身体障害者手帳の等級分類
身体障害者手帳の等級は、1級から7級までに分類されており、数字が小さいほど障害の程度が重いことを示します。手帳の交付対象となるのは6級までで、7級単独では交付の対象になりません。
しかし、7級の障害が複数重なっている場合や、異なる等級の障害が複数あり、6級以上の障害と重複している場合には、手帳が交付されるケースもあります。
また、障害の種類によっては1級や5級が設定されていない場合や、7級が存在しない場合もあります。例えば、聴覚障害には7級が設けられておらず、最も軽い障害でも6級となるなど、分類は一律ではありません。
等級の判断は、身体障害者福祉法に基づいた基準に従って行われ、医師の診断書をもとに審査されます。
身体障害者手帳の等級別の特性

身体障害者手帳の等級について理解することで、「どのような支援が必要なのか」「雇用や就労支援においてどのような配慮が求められるのか」が見えてきます。
ここでは、等級ごとの障害の程度や行動可能な範囲、生活上の困難さについて解説します。
等級ごとの行動可能な範囲
身体障害者手帳の等級は、障害の部位や種類ごとに異なります。おおよその目安として、障害の程度と必要な支援について以下の表でまとめました。
| 等級 | 障害の程度の目安(一部) | 必要な支援 |
|---|---|---|
| 1級 | 重度の障害。両眼の視力の和が0.01以下。両手足の機能がまったく使えない状態や、内臓・免疫・肝機能などの障害により、日常生活をほぼ自力で行えないレベル | 食事・更衣・移動・排泄といった日常生活のほとんどに支援を要する |
| 2級 | 重度の障害。両眼の視力の和が0.02以上0.04以下、または両耳の聴力が100デシベル以上(両耳全ろう)で、会話がほぼ不可能。両手足に著しい障害がある場合や、内臓・免疫障害で日常生活が大きく制限される状態 | 屋内移動や衣食住の一部において介助が必要。歩き続ける・座り続ける・立ち上がることが困難 |
| 3級 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下。両耳で90デシベル以上の難聴。発声や言語機能を失っている場合や、一方の手や足に重大な障害がある場合など。家庭内での生活にも支障をきたすレベル | ある程度自立は可能だが、歩行や作業などで著しい制限がある。日常生活には部分的な支援が必要で、身体的負担の大きい作業は困難 |
| 4級 | 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下。両耳で80デシベル以上の難聴。発音・咀嚼(そしゃく)機能の著しい障害、両手の親指を欠いている場合や、足の指すべてを失っている場合など。社会生活に明らかな支障がある | 就労は可能だが業務の内容に配慮が求められる。生活の一部で不便を感じることが多い |
| 5級 | 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下 。平衡感覚や体幹の著しい障害、片足の膝や股関節の機能障害、両手の親指に大きな機能障害がある状態など | 特定の動作や作業に制約があるが、基本的な日常生活は自立可能 |
| 6級 | 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が 0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超える。片手の親指や片足の足関節の機能に障害がある状態。両耳で70デシベル以上の難聴など | 日常生活で困難が生じる場面がある |
各障害/等級ごとの障害程度は、厚生労働省「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」をご覧ください。
出典:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」
等級ごとの困難さ
1~3級に該当する方は、生活の多くの場面で支援が必要です。具体的には、食事・入浴・着替えといった基本的な動作を自分ひとりで行うことが難しく、常時または頻繁に介助を受ける必要があります。また、通院や買い物なども単独では難しいケースがほとんどです。
4級と5級は、ある程度の自立生活は可能ですが、社会活動や仕事などになると制約が多くなります。長時間の立ち仕事や歩行、複雑な作業には困難を感じやすく、特定の職務には就きにくいこともあります。
6級の場合は、日常生活をひとりで送ることができる場合が多いものの、視力や聴力、片手の細かい動きなどに支障をきたしている状態です。周囲からは障害がわかりづらいため、本人が苦労していることが見落とされやすい等級でもあります。
身体障害者手帳の「等級」に関わる障害者雇用のルール

企業が障害者を雇用する際、どのような方が「障害者」としてカウントされるのかは法律で定められています。「障害者雇用促進法(正式法令名 :障害者の雇用の促進等に関する法律)」では、身体障害・知的障害・精神障害を持ち、長期にわたり職業生活に制限があると認められた方を「障害者」と定義しています。
実際に雇用率の対象としてカウントできるのは、次のいずれかの手帳を所持している方です。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
ただし、身体障害者手帳の場合、等級によって雇用数のカウント方法が異なるため、注意が必要です。ここでは、障害者雇用義務数の求め方や、実雇用率の計算、等級別のカウント方法について解説します。
出典:厚生労働省「障害者雇用率制度について」
障害者の雇用義務数の計算方法
企業には、一定割合の障害者を雇用する義務があります。これを「法定雇用率」と呼びます。2025年時点での民間企業の法定雇用率は2.5%ですが、2026年7月からは2.7%に引き上げられる予定です。雇用義務数の計算式は以下の通りです。
・障害者の雇用義務数 =(常用労働者数 + 短時間労働者数 × 0.5) × 2.5%
※「常用労働者」には短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)は含まれません。
実際の障害者雇用率の計算方法
実際に自社がどれだけ障害者を雇用できているかを把握するには、実雇用率を計算します。
・障害者の実雇用率 =(障害者である常用労働者数 + 障害者である短時間労働者数 × 0.5) ÷
(常用労働者数 + 短時間労働者数 × 0.5)
※「常用労働者」には短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)は含まれません。
上記の計算により、企業が法定雇用率を満たしているかどうかを判断できます。
等級別のカウント方法
身体障害者手帳を持っている方のうち、どのようにカウントされるかは、等級や労働時間によって変わります。
| 週30時間以上 | 週20~30時間未満 | 週10~20時間未満 | |
|---|---|---|---|
| 重度身体障害者(1級・2級、または3級の重複障害) | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 身体障害者(上記以外) | 1人 | 0.5人 | – |
法定雇用率の達成に向けて、人数が不足している場合は、「農園型 障害者雇用支援」を検討するのも有効な手段のひとつです!


まとめ
身体障害者手帳は、障害の種類や程度を示す大切な公的証明書です。その等級ごとの違いは、支援内容だけでなく、企業における障害者雇用にも直結します。特に雇用数のカウントでは、等級や労働時間によって評価が異なるため、採用時や雇用管理の際には注意しましょう。
本記コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。