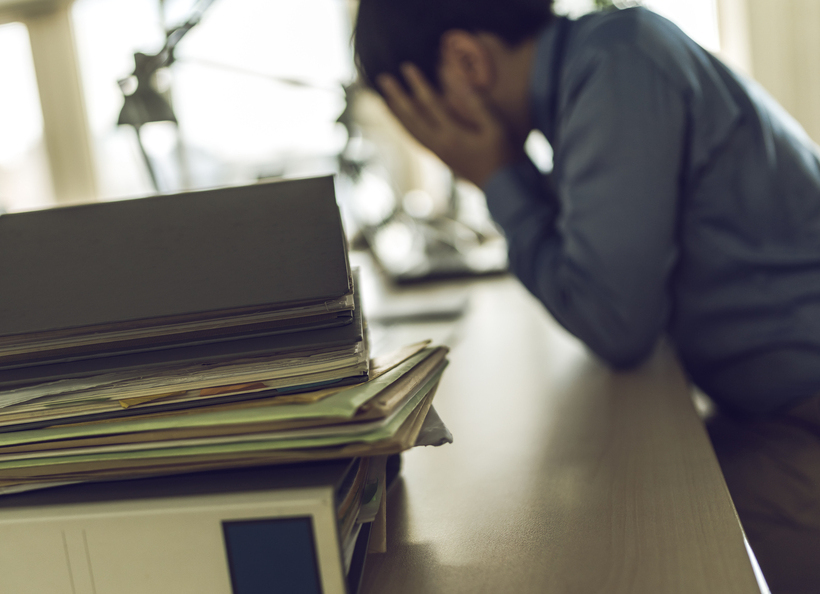農園型障害者支援とは、農業と福祉を結びつけた「農福連携(のうふくれんけい)」という取り組みのひとつで、障害者の社会参加や自立支援を目的とした新しい雇用のかたちです。
政府もこの取り組みに力を入れており、2016年には「共生社会」の実現を目指す政策の一環として農福連携を推進しました。さらに2024年には「農福連携等推進ビジョン」の改訂版が発表され、その広がりはますます加速しています。
今回は、農園型障害者支援の仕組みや注目されている背景、企業側・障害者側のメリットについてわかりやすく解説します。
「農福(農業×福祉)連携」のひとつ農園型障害者雇用とは

障害者の就労支援と農業振興を両立させる新たな取り組みとして注目されている「農園型障害者雇用」ですが、その仕組みについて詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。まずは農園型障害者雇用の概要と仕組みについてみていきましょう。
農園型障害者雇用の概要
農園型障害者雇用とは、企業が外部の支援業者から農園を借り受け、障害者の就労環境を整える雇用モデルのことです。企業は障害者を直接雇用しつつ、日々の作業場である農園の管理や業務のサポートは支援業者に委ねることで、安心して雇用を継続できます。
農園という自然に囲まれた環境は、心身の健康にも良い影響を与え、特に屋内での作業が苦手な人や軽作業を希望する人にも適しています。また、企業にとっては障害者雇用義務の達成や雇用継続の課題を解決でき、社会的責任を果たす手段としても注目されています。
農園型障害者雇用の仕組み
農園型障害者雇用は、企業と支援業者、障害者の三者が連携して成り立つ仕組みです。以下の4ステップで構成されています。
1.企業と支援業者の契約
- 企業は、障害者雇用の受け入れを前提に支援業者と契約を結ぶ
- 支援業者は農園を用意し、必要な設備や作業内容を整備する
- 障害者の紹介や就労開始時のサポートも支援業者が担う
2.採用活動
- 支援業者が就労可能な障害者を企業へ紹介する
- 企業が選考を実施し、該当者と直接雇用契約を締結する
3.農園での就労開始
- 雇用された障害者は、農園で農作業に従事する
4.農園運営と継続支援
- 支援業者が農園全体の管理・運営を担当し、企業に対して雇用継続に関するアドバイスを行う
- 企業の担当者は、業務指導や雇用管理を担う
- 障害者への業務指導や勤怠管理までも支援業者が代行するケースもある
農園型障害者雇用が注目されている背景

障害者雇用をめぐる環境は年々変化しており、多くの企業が対応に迫られています。そうした中で「農園型障害者雇用」は、障害者の安定した就労と企業の法定雇用率達成の両立を可能にする仕組みとして注目されています。続いて、農園型障害者雇用が広がっている背景をみていきましょう。
1.法定雇用率の引き上げ
障害者雇用促進法により、一定規模以上の企業は「障害者を一定割合以上雇用する義務」があります。これを「法定雇用率」と呼びます。
近年、この法定雇用率は段階的に引き上げられており、2025年6月現在の民間企業における法定雇用率は2.5%です。さらに、2026年7月には2.7%へと引き上げが予定されています。また、対象となる事業主の基準も見直され、従業員数40.0人以上から37.5人以上へと範囲が拡大する予定です。
こうした中、厚生労働省のデータによると、2024年時点で法定雇用率を達成している企業は全体の約46%にとどまっており、半数以上の企業が未達成というのが現状です。農園型障害者雇用は、企業が無理なく法定雇用率を達成する手段として注目を集めています。
出典:
厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」
2.障害者雇用のノウハウ不足
障害者の雇用に初めて取り組む企業では、以下のような悩みが多く聞かれます。
- どのような仕事を任せれば良いかわからない
- 障害の種類や特性に応じた業務設計が難しい
- 社内の受け入れ体制や支援体制が整っていない
- 教育に時間やコストがかかる一方で、なかなか定着しない
こうした背景から、障害者雇用へのハードルを感じている企業は少なくありません。農園型雇用では、支援業者が農園運営から人材紹介、職場環境づくり、継続支援などをサポートしてくれます。
そのため、企業は農業という業務フィールドを活用しつつ、専門的な支援を受けながら障害者雇用に取り組むことが可能です。そして、ノウハウ不足による不安の軽減にもつながります。
3.働きやすく職場定着しやすい農作業の特性
農園型障害者雇用の大きな特徴は、「農作業」という就労環境自体が、障害者にとって相性の良い業務である点です。以下のような特性が、働きやすさや定着率の高さにつながっています。
- 水やり、収穫、除草、清掃といった、定型的でストレスの少ない作業が多い
- 障害の特性や得意・不得意に応じた作業の割り振りがしやすい
- 人との接触が少なく、自分のペースで作業できる環境が整っている
このように、農作業は精神的・身体的な負担が比較的少なく、継続しやすい業務といえます。企業にとっても、離職率の低下や長期的な雇用安定につながるため、魅力的な選択肢といえるでしょう。結果として、企業と障害者の双方にとって続けやすい雇用モデルとして支持が広がっています。
農園型障害者雇用のメリット

農園型障害者雇用は、従来の障害者雇用の課題を解決しながら、企業と障害者の双方に多くのメリットをもたらす仕組みです。
企業にとっては「スムーズな雇用」「高い定着率」「社会的評価の向上」などの利点があり、障害者にとっても「安心して働ける環境」「明確な業務内容」「継続しやすい職場」といった魅力があります。ここでは、それぞれの立場からみたメリットを解説します。
利用する企業側のメリット
農園型障害者雇用は、支援業者が農園の運営から人材紹介、就労支援までを一括で担ってくれるため、社内の体制が整っていなくても障害者雇用をスムーズに始められる点がメリットです。
また、支援業者が紹介してくれる人材は、農作業への適性や希望がある人が多く、マッチングの精度が高いことから、早期離職のリスクを抑えられます。農作業という安定した業務に従事することで、職場定着率が高くなりやすいのも特徴です。
さらに、障害者雇用を積極的に進める姿勢は、企業の社会的信用やブランドイメージ向上にも直結します。
従事する障害者側のメリット
農園型障害者雇用は、障害者本人にとっても働きやすく、安心して長く続けられる環境が整っています。先述のように農作業は比較的ストレスの少ない、定型的な作業が中心です。手順が明確に決まっており、かつ集中しやすい作業内容が多く、精神的な負担がかかりにくい側面があります。
また、屋外でのびのびと作業できるケースが多く、自分のペースで働けるため、無理なく就労を続けられる点も大きな魅力です。さらに、支援業者や企業の担当者による定期的なフォローや相談体制が充実していることが多く、安心して働ける環境が整っています。
ステップアップも見据えた農園型障害者雇用「めぐるファーム」の特徴
障害者雇用に取り組む企業にとって、「どのように始めるか」、「どのように定着させるか」は大きな課題です。そうした課題を一括で支援するのが、農園型障害者雇用プラットフォーム「めぐるファーム」です。屋外ハウスを活用した就労環境を提供し、企業と障害者双方にとってメリットのある支援サービスを展開しています。
めぐるファームは、半径約10km圏内にある就労支援センターや就業・生活支援センターと密接に連携しており、各センターから常時、適切な人材の紹介が可能な体制を整えています。障害のある方は、整備された栽培設備のあるハウスやオフィスで、葉物野菜や果菜類を育てる業務に従事可能です。
単なる作業者にとどまらず、育成管理を担うことで、より高い意欲と責任感を持って働ける環境を提供しています。
特徴1|企業への手厚いサポート体制
めぐるファームでは、障害者雇用が初めての企業でもスムーズに導入できるよう、多面的かつ柔軟なサポート体制を用意しています。
企業のニーズに合わせて管理スタイルや運営方法を柔軟に設計しており、例えば企業側が管理者を派遣する場合には、事前にめぐるファームが研修を実施して円滑な運営を後押しします。
また、栽培する作物やその活用方法についても企業と相談しながら決めていくため、社内での福利厚生や地域への貢献など、企業独自の活用が可能です。定着面談も実施し、本社から離れた場所でも帰属意識を持てるようにサポートします。
特徴2|障害者へのスキルアップ支援
めぐるファームは、障害者の就労支援にとどまらず、将来を見据えたスキルアップの機会を大切にしています。国家資格を持つ専門スタッフをはじめとした最大6名の常駐スタッフが、障害者の方の業務を丁寧にサポートし、それぞれのペースや得意分野に応じた成長を促します。
本コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。