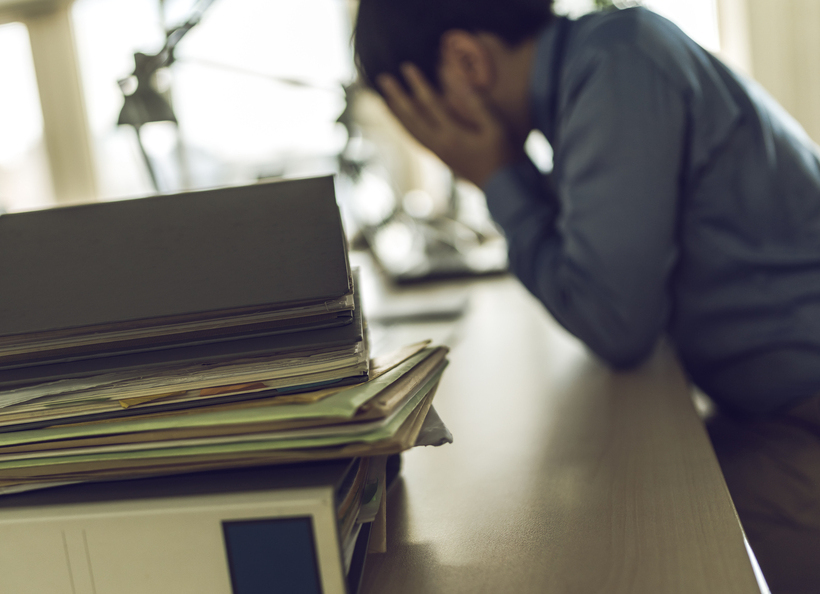障害者の法定雇用率が2026年7月には2.7%へ引き上げられるにあたり、業務設計や職場環境の整備に課題を感じている企業も多いのではないでしょうか。
今回は、企業と障害者の双方が抱える主な課題を整理した上で、障害者雇用を成功させるためのポイントを解説します。新しい形態として注目される「農園型障害者雇用支援サービス」についても紹介しますので、障害者雇用の担当者の方はぜひご覧ください。
障害者雇用において企業が直面しやすい課題

障害者雇用の推進が期待される一方で、多くの企業が何らかの課題に直面しています。月刊総務の調査によれば、企業は障害者雇用について課題を「とても感じている(61.0%)」「やや感じている(19.5%)」と回答しています。
近年では精神障害者の雇用数が急増しており、厚生労働省の令和6年度調査では、前年比15.7%増と発表されました。こうした現状において、精神障害者の雇用に課題を感じている担当者の方も少なくないでしょう。
まず、多くの企業が直面している障害者雇用の主な課題について解説しましょう。
出典:
株式会社月刊総務「8割以上が障がい者雇用に課題を感じているものの、7割以上が「適性・能力に合った仕事を割り振れている」と回答。受け入れ部門は管理部門が7割。」
厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」
社内の環境が整っていない
令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されました。しかし、その対応が追いついていない企業も少なくありません。
合理的な配慮の例として、エレベーターやスロープ、車椅子対応のトイレの設置といった物理的なバリアの除去があります。マニュアルの作成や作業手順の簡素化などは、業務面への配慮の例です。
そのほか、視覚障害の方を対象とした音声読み上げソフト、聴覚障害の方向けの筆談ツールなどを導入している企業もあります。
とはいえ、合理的配慮の準備には時間と手間を要することから、現場レベルでの理解や協力が得られにくいという課題があります。そのため、企業の受け入れ態勢については、ばらつきがあるのも事実です。
採用が難しい
企業側が身体障害者や知的障害者の採用を目指す方針であったとしても、実際の採用市場では精神障害者が圧倒的に多いため、そのギャップに課題を感じる採用担当者の方もいます。福利厚生が充実している大手企業に求職者が集中する傾向は一般求人と同様です。
また、特に東京都では有効求人倍率が高く、採用が難しい状況にあります。
採用難に直面している企業のなかには、ハローワークだけに求人を出しているケースも多くみられます。このような場合、求職者の目に留まりにくく、結果として採用機会を逃している可能性も否めません。
依頼できる業務がない・切り出しが難しい
企業側が抱える課題のひとつに、業務の切り出し作業があります。必要な合理的配慮は個別性があり、同じ作業でも障害の特性によって状況が異なるため、適切な業務の割り当てが難しいからです。
月刊総務の調査では、「障害者雇用にどのような課題を感じているか」という設問に対して、68.2%の企業が「業務の切り出し」と回答。「適性・能力が発揮できる仕事への配置」が63.6%と続きました。
厚生労働省の調査では、身体障害者の雇用上の課題を問う設問に対して、「会社内に適当な仕事があるか」という回答が77.2%で最多でした。
出典:
PR TIMES「8割以上が障がい者雇用に課題を感じているものの、7割以上が「適性・能力に合った仕事を割り振れている」と回答。受け入れ部門は管理部門が7割。」
厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」
社内の理解が不足している
特別な配慮が必要な障害者雇用は業務の負担になりかねない、といった偏見は、多くの企業に根強く残っています。社内の意識改革が追いつかず、障害者雇用に積極的でない企業も少なくありません。
とりわけ精神障害は、症状が外観からわかりにくいという特徴があります。結果として、周囲から「どのような配慮が必要かわからない」「接し方が難しい」などのイメージをもたれやすく、現場での協力がうまく得られないケースもみられます。
障害者への理解が不足した環境では、障害者自身も働きづらさを感じやすく、早期退職につながりかねません。企業全体での理解促進が不可欠です。
定着率が低い
定着率の低さも障害者雇用の課題です。職場環境とのミスマッチにより、早期離職につながるケースがあります。
高齢・障害・求職者雇用支援機構の調査によると、就職後1年経過時の職場定着率は平均で63%です。最も定着率が低いのは49.3%の精神障害で、2人に1人が1年後に離職している可能性が高いと考えられます。
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者の就業状況等に関する調査研究」
障害者雇用において障害者が直面しやすい課題

次に、障害者が直面する課題について見ていきましょう。
求人が少ない
障害者求人は一般求人と比較して数が限られます。特に福利厚生や設備が充実している大手企業に応募が集中し、わずかな募集枠に多数の応募者が殺到するため、競争率が高くなる傾向にあります。
結果として、障害者側は希望する職種や条件での就労が難しく、就職活動が長期化することも珍しくありません。
賃金・待遇が低い
非正規雇用や短時間勤務が多く、賃金が抑えられやすい傾向にあることも、障害者が直面する重要な課題です。
厚生労働省の調査によると、身体障害者の1か月あたりの平均賃金は23万5,000円と20万円を超えたものの、知的障害者・精神障害者・発達障害者は10万円台にとどまっています。
| 障害の種類 | 平均賃金 |
|---|---|
| 知的障害者 | 13万7,000円 |
| 精神障害者 | 14万9,000円 |
| 発達障害者 | 13万円 |
一方、「令和6年賃金構造基本統計調査」では、一般労働者の平均賃金は33万円(男性36.3万円、女性27.5万円)との結果が出ています。依然として障害者と一般労働者の平均賃金には大きな差がある状況です。
そのほか、満足のいく就労条件や職場環境が提供されにくいなど、待遇面での課題もみられます。
出典:
厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
キャリア形成が難しい
障害者雇用では業務が限定されやすく、スキルアップや仕事の幅を広げることが難しい点も課題です。一般労働者と比較して昇進や昇格の機会が少ないという実情もあります。
また、障害者を対象とした中長期的な人材育成の制度がない企業もあり、障害者の能力や可能性を引き出す環境が整っていないケースが散見されます。
フルタイム勤務が難しい
厚生労働省の調査によると、障害者雇用で最も多く見られる勤務時間は週30時間以上です。
その理由のひとつが法定雇用率の算定です。法定雇用率を算定する際に、週所定労働時間が30時間以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者は1名分、重度身体障害者、重度知的障害者は2名分と換算されます。
障害の種類によっては短時間勤務だと0.5名に換算される場合があり、法定雇用率を上げたい企業にとっては、30時間以上勤務できる方を採用したい意図があるためです。
とはいえ、障害の特性によっては、週30時間以上の勤務が現実的でないこともあります。特に精神障害者は急な体調の変化が起こりやすく、定期的な通院や服薬が必要な方も多くみられます。
上記のような事情から、フルタイム労働者を採用したい企業と障害者との間にギャップが生じています。
出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」
不安やストレスを抱えてしまう
働く障害者の中には、体調管理や職場環境への適応について不安を感じる方もいます。
特に精神障害のある方については、職場での適切な配慮や支援体制が不十分な場合、不安やストレスが就業継続に影響を与えることがあります。
その結果、職場環境や周囲の理解不足により、本来持っている能力を発揮しにくい状況が生じる場合があるのです。
障害者雇用を成功させるための3つのポイント

安定した障害者の就労を実現し、法定雇用率の達成を果たすために企業が取り組むべき3つのポイントを紹介します。
経営ビジョンを反映した障害者雇用方針をもつ
障害者雇用を成功させるには、まず企業文化として根付かせる必要があります。そのためには、単なる法定雇用率を達成する上での義務と捉えるのではなく、障害者雇用を企業理念や社会への提供価値と結びつけることが重要です。
従業員に対して経営ビジョンに基づく障害者雇用の方針を明確に示せば、全社的な協力体制の構築につながり、障害者雇用への理解も深まるでしょう。
採用時には業務と環境の両面をすり合わせる
入社後のトラブルや早期離職を防ぎ、障害者の安定的な雇用を実現するためにも、障害のある方が安心して働ける職場環境の整備が欠かせません。その際に重要となるのが、採用時や配属前のすり合わせです。
この段階で障害特性や職務能力、配慮事項、適切なコミュニケーションの取り方などを企業側が把握し、受け入れ体制に反映させることが、ミスマッチを防ぐ鍵となります。
配属先を支援して受け入れ体制を強化する
配属先への継続的なフォローも、雇用の定着を図る上で必要な対策です。配属先の上司やスタッフと障害特性や配慮事項について事前に共有し、上司との定期的な面談の機会を設けることで、問題の早期発見と対処が容易になります。
さらに、トラブルが発生した場合に備えて、専門家や外部機関へつなぐ基準や対応フローを明文化しておけば、配属先の担当者の心理的な負担も軽減できます。
障害者雇用の課題を乗り越える「第二の選択肢」とは
障害者雇用の受け入れ体制の整備が難しい場合は、農園型障害者雇用支援サービスの活用も有効な手段です。
農園型障害者雇用支援サービスは、支援業者が農園を貸し出し、障害者は導入企業の従業員として農園で就労する仕組みです。導入企業が管理監督を行うことで法定雇用率にカウントされるだけでなく、農園側の各種サポートも受けられます。
農園型障害者雇用支援サービス「めぐるファーム」では、国家資格者をもつ専門常駐スタッフを中心としたチームがサポートにあたっています。屋外農園の「開放感」と屋内農園の「清潔感」を兼ね備えたハウスで快適に働ける環境です。
農作業は業務の切り出しがしやすく、個々の特性に応じた働き方ができることから、精神障害のある方にとって働きやすい環境となっています。障害者雇用に関する課題を抱えている事業者様は、ぜひ一度お問い合わせください。
まとめ
障害者雇用を取り巻く課題は多岐にわたります。企業は、それらの課題を整理し、対応策を講じていくことで、障害者の安定的な雇用の実現や法定雇用率の達成につなげられるでしょう。
自社での体制整備が難しい場合には、農園型障害者雇用支援サービスをはじめとする外部リソースの活用も視野に入れると良いでしょう。障害者雇用に関する課題を乗り越えるため、自社にとって適切かつ継続的に実践できる方法を検討してください。
本コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。