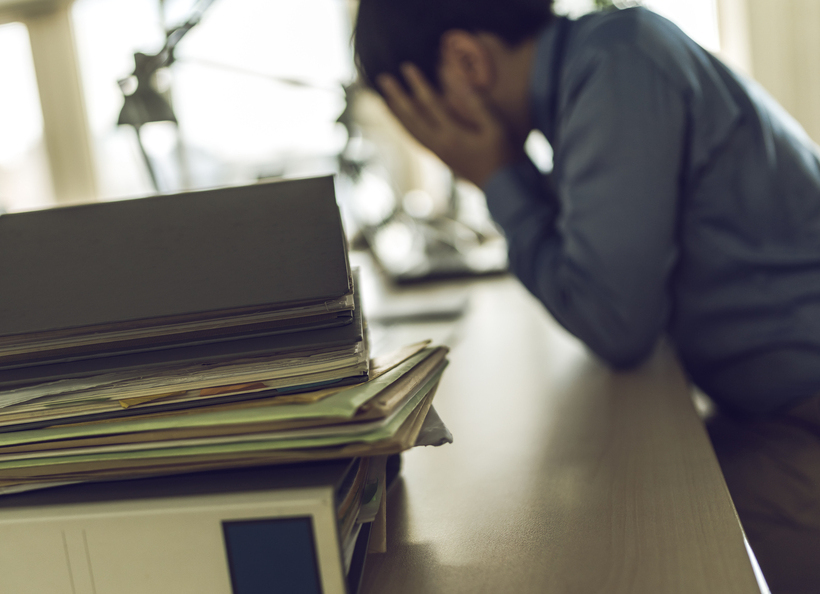障害者雇用とは、障害のある方を企業や自治体などで雇用する制度のことであり、障害者雇用促進法によって定められています。障害者雇用の推進が求められる中で、障害者雇用の内容や始め方について理解が不十分な方もいらっしゃるでしょう。
今回は、障害者雇用の概要や一般雇用との違い、障害者雇用を始める前に知っておくべきポイントについて解説します。
障害者雇用とは?

障害者雇用の概要や、一般雇用との違いについて紹介します。
障害者雇用の概要
障害者雇用とは、企業や自治体などが別枠を設けて障害のある方を雇用し、個々の特性に合わせた働き方を可能にする制度です。
障害のある方が、障害のない方と同じような仕事内容、勤務時間などの条件で働くことは、障害の内容や状態、特性により難しい場合があります。
そこで障害者が就業する機会を得やすくするため、「障害者の雇用の促進等に関する法律(以降:障害者雇用促進法)」により定められたのが障害者雇用です。
厚生労働省は、障害者雇用の理念として「共生社会の実現」「貴重な労働力・戦力の確保」「企業全体の生産性向上・マネジメント力の強化」の3点を掲げています。障害に関係なく、誰もが希望や能力に応じた職業を通して社会参加ができる共生社会をつくっていく必要があるのです。
一般雇用との違い
一般雇用とは、企業の応募条件を満たせば誰でも応募できる求人で、障害者手帳の有無に関わらず応募できます。求人や職種が豊富である一方、障害への理解や配慮が職場で得られにくい可能性があります。
対して障害者雇用とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方向けの求人です。障害の特性を企業が把握した上で採用するため、仕事に取り組む際に周囲からの配慮を受けやすくなります。
また、障害者手帳を持っている方が一般求人で就業するケースもありますが、障害者枠での就業のほうが1年後の定着率は高い傾向にあります。
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター「障害者の就業状況等に関する調査研究」
障害者雇用の対象者
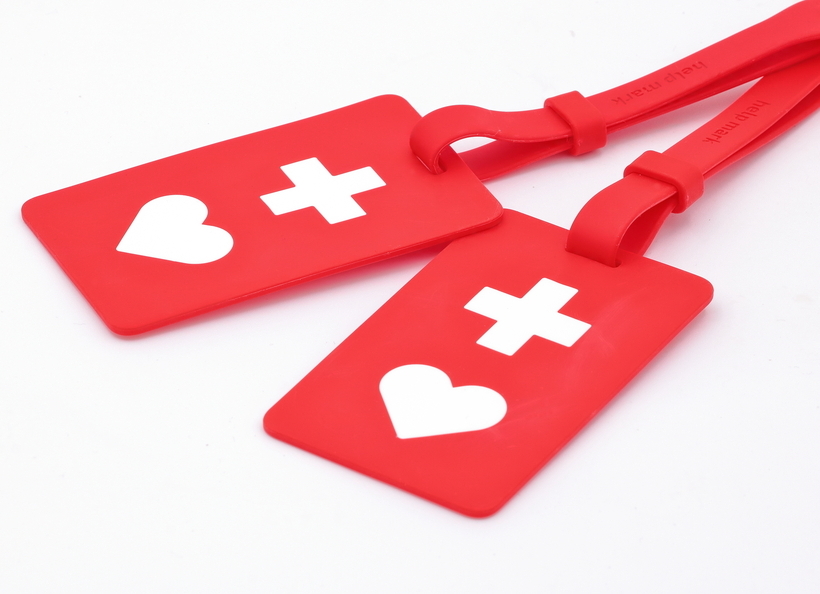
障害者雇用の対象者は以下の通りです。
- 身体障害者(身体障害者手帳の1~6級を所持する方)
- 知的障害者(児童相談所などで知的障害者と判定された方)
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方)
なお、たとえ上記と同様の障害があっても、手帳を所持していない場合は障害者雇用の対象にはなりません。原則として、障害者雇用は「障害者手帳」を所持している方が対象となります。
また障害者手帳を持っている場合は、一般求人と障害者雇用の求人の両方に応募できます。
出典:厚生労働省「障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象」
障害者雇用を推進するメリット
障害者雇用率を達成することは、障害者雇用促進法を遵守するだけでなく、企業の発展や成長に役立つというメリットがあります。
具体的なメリットは以下の通りです。
- ブランドイメージの向上
- 多様性ある社会づくりへの貢献
- 多様な人材の獲得
企業が障害者雇用率を達成し、障害者が活躍している企業であると示すことは、社会的責任を果たしている証明にもなります。
また、障害者雇用によって多様な人材がともに働くことで、会社の多様性だけでなく、労働力不足にも対応できます。そして一人ひとりの能力を発揮できる環境を整えることで、新しい発想や価値の創造が期待できるでしょう。
障害者雇用のメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
障害者雇用を始める企業が知っておくべきこと

ここからは、障害者雇用を始める企業が基礎知識として押さえておきたい事項を紹介します。
必要雇用数・実雇用数の計算方法
民間企業や国・地方公共団体に義務づけられている障害者の雇用人数は、障害者雇用促進法により「法定雇用率」として定められています。法定雇用率とは、一般の労働者のうちどれくらいの割合で障害者を雇用する必要があるかを定めた基準のことです。
法定雇用率の計算式は以下の通りです。
- 障害者法定雇用率=(対象障害者である常用労働者の数+失業している対象障害者の数)/(常用労働者数+失業者数)
法定雇用率は、労働市場の状態や経済状況に応じて、およそ3〜5年ごとに引き上げられる傾向にあります。民間企業では2013年に2.0%、2018年4月に2.2%、2021年3月に2.3%、2024年4月に2.5%と徐々に引き上げが行われてきました。今後は2026年7月に2.7%に引き上げられる予定です。
出典:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
以下の記事で、障害者の雇用率について詳しく解説しています。
法定雇用率を達成できない場合のペナルティ
常用労働者が100名を超える民間企業において障害者法定雇用率が達成できていない場合、納付金支払いの義務が生じます。雇用人数が不足している障害者数に応じ、1人当たり月額5万円の障害者雇用納付金を納めなければなりません。
納付金の目的は、障害者の雇用数を達成している企業と、未達成の企業の経済的負担を調整することであり、罰金とは異なります。納付金を払ったとしても障害者を雇用する義務は残ることに注意が必要です。
法定雇用率を達成できていない企業の事業主に対してはハローワークから行政指導が行われ、それでも改めない場合は厚生労働省による特別指導を経て社名が公表されます。
一度社名が公表されると会社のイメージダウンにもつながってしまうため、企業は積極的に障害者雇用に取り組む必要があります。
障害者雇用の納付金について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
障害者雇用で活用できる助成金
職場のバリアフリー化やユニバーサルデザインの導入など、障害者が安全に働けるような職場環境を整える際には、助成金制度を利用するのがおすすめです。
助成金には以下のような種類があります。
- トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース/障害者短時間トライアルコース)
トライアル雇用助成金は、原則3か月間の試行期間を経て障害者を雇用する「トライアル雇用」を実施する企業に支給されます。
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース/発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
特定求職者雇用開発助成金は、ハローワークなどの職業紹介では就職が困難と考えられる障害者や高齢者など、特定の条件を満たした求職者を雇用した企業に支給される助成金です。
障害者雇用助成金は、障害者の雇い入れや雇用の継続にあたって事業主が対応する際に、それぞれの条件をクリアすることで支給されます。
出典:厚生労働省「障害者を雇い入れた場合などの助成」
障害者雇用の助成金について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
障害者雇用に関する相談先
障害者雇用に関する相談先は以下の通りです。
- ハローワーク
ハローワークは全国544か所(令和7年度時点)にあり、障害者の態様に応じた職業紹介や職業指導、求人開拓などを行っています。また障害者を雇用している事業主や、雇用を検討している事業主に対して、雇用管理に関する助言も行っています。
- 地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは47都道府県に設置されており、障害者職業カウンセラーによる障害者に対する職業評価や職業準備支援、事業主への障害者雇用に関する専門的な支援を行っています。
- 障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは全国337か所(令和7年6月時点)にあり、障害者の身近な地域において、就業面と生活面の相談・支援を実施しています。また、事業主からの雇用管理についての相談も受け付けています。
- 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者や高年齢者などを雇用する事業主に対して相談や援助などさまざまな支援サービスを提供しています。
出典:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者の雇用支援」
障害者雇用支援の選択肢
障害者雇用に関して社内の態勢を整えるのが難しい場合は、障害者雇用支援サービスを使用するのもひとつの手段です。中でも近年注目を集めているのが、農園型障害者雇用支援サービスです。
農園型障害者雇用支援サービスとは、サービスを提供する支援業者が、障害者雇用を促進したい企業に農園を貸し出し、そこを障害者雇用の場として活用するサービスを指します。
障害者を雇用した事業主が給与や社会保険の責任をもつ一方、普段の業務管理やサポートは支援業者が行うのが特徴です。企業が障害者を雇用しているという形は変わらないため、障害者の法定雇用率にもカウントされます。
農園型障害者雇用支援サービスについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
「障害者雇用めぐるファーム」は、快適な環境を整備したスマート農園で、障害のある方と企業をつなぐ農園型障害者雇用支援事業です。障害のある方が施設内で農作業などを行い、仕事の指導や生活面の支援を受けながら将来的な自立を目指します。
また障害者だけでなく管理者向けの研修も用意しており、未経験でも雇用管理が可能になるよう支援いたします。
障害者の雇用に不安がある人事担当者の方は、ぜひこちらをご覧ください。
まとめ
障害者雇用とは、企業や自治体などが障害のある方を雇用し、個々の状態や特性に合った働き方ができるようにすることです。障害者雇用の推進によって、企業の発展・成長、ブランドイメージの向上などにつながるというメリットがあります。
障害者雇用による職場環境の整備が困難な場合は助成金の活用や、支援サービスへの相談が可能です。
また、外部就労支援の農園型サービスを利用するという選択肢もあるので、障害者雇用でお悩みの方は検討してみても良いでしょう。
本コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。