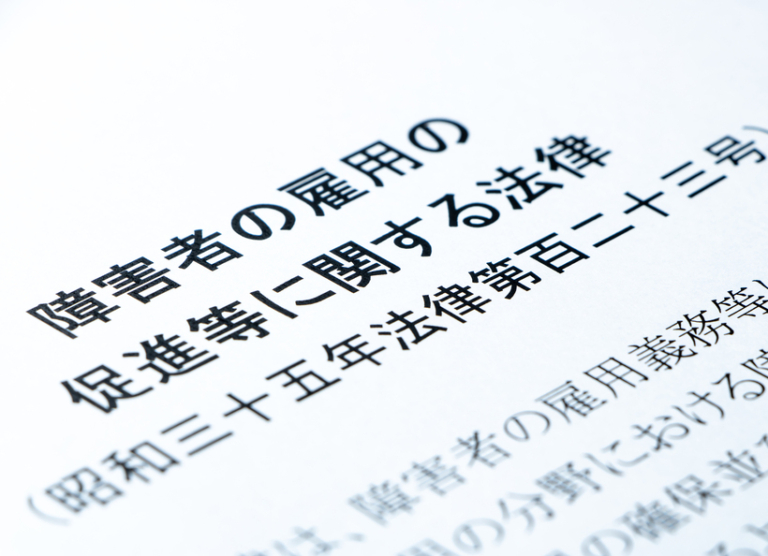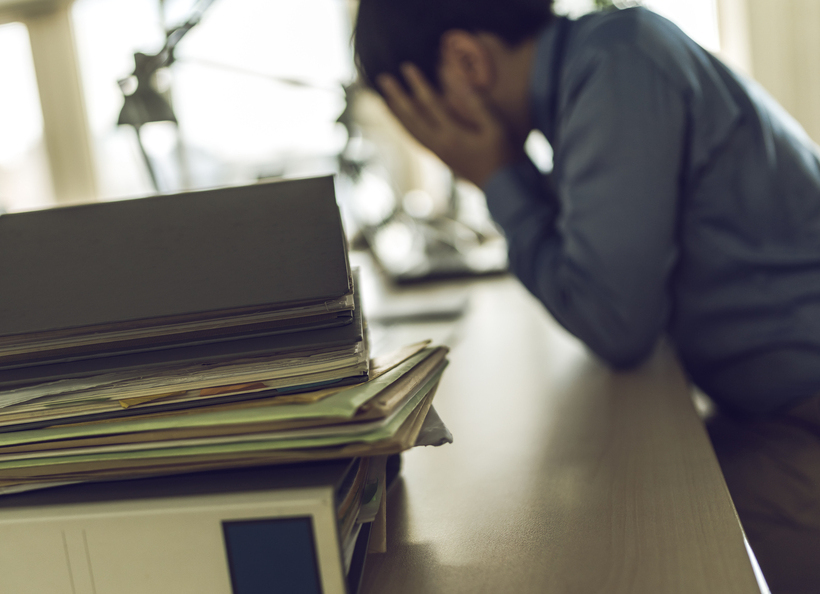障害者の雇用を進めることは、多様性を重視した組織づくりや、企業イメージの向上など、企業にとって多くのメリットがあります。一方で、「法律で義務づけられているから」という理由だけで雇用に踏み切る企業も少なくありません。今回は、障害者雇用のメリットや導入する際の課題、成功へ導くためのポイントを紹介します。
障害者雇用を進める5つのメリット

障害者雇用は、法令遵守だけでなく、企業の成長や社会的価値の向上につながる重要な取り組みです。まずは、企業が障害者雇用を推進することで得られる主なメリットを5つ紹介します。
企業イメージが向上する
障害者雇用に積極的に取り組む姿勢は、企業の社会的責任(CSR)を果たす上で欠かせない要素です。自社の利益だけでなく、ステークホルダー(消費者や投資家、社会全体の利害関係者)に対して配慮している企業として評価されることで、企業の信頼性やブランド価値が高まります。
また、CSR報告書において、ダイバーシティ推進の観点から女性やシニア、外国人と並んで障害者の活躍を紹介する企業も増えてきました。
このような企業の取り組みは、求職者や取引先、投資家からの共感や信頼を得やすくなり、優秀な人材の確保やビジネスチャンスの拡大にもつながります。
ダイバーシティ経営を実現できる
ダイバーシティ経営とは、多様な人材を積極的に受け入れ、イノベーションや企業成長につなげる経営手法です。経済産業省も企業の持続的成長のために、重要な取り組みと位置づけています。
障害者雇用の推進は、年齢や性別、国籍に加え、障害の有無にかかわらず一人ひとりの潜在的な能力や特性を活かせる職場づくりに直結します。自由な発想が生まれやすくなり、業務効率や企業の競争力を高めることにつながるのです。
出典:経済産業省「ダイバーシティ経営の推進」
人手不足への対応につながる
少子高齢化の影響で、国内の労働力不足は深刻な問題となりつつあります。その中で、障害者を含む多様な人材の活用は、企業が今後も安定した事業運営を続けていくための有効な手段といえます。
シニア層や短時間勤務の雇用が注目される一方で、障害者雇用も労働力不足を補う貴重な人材として期待されています。障害者雇用に前向きに取り組み、多様な人材が協力して働く体制を整えることで、今後深刻化する人材不足への備えにもなるでしょう。
業務フローの見直しや業務効率化を図れる
障害者の雇用をきっかけに、業務内容を見直す企業は少なくありません。これまで見過ごされていた社内業務を整理することで、無駄を省き生産性を高めることも可能です。
これらの取り組みにより、業務全体の最適化につながることがあります。また、業務フローを再設計することで、障害者に無理なく任せられる仕事をつくることもできます。
税制優遇や助成金を受けられる
障害者雇用を進める企業には、国や地方自治体からの助成金や奨励金など、金銭的な支援があります。
障害者を雇用する際に得られる助成金のほかにも、職場の設備を整えたり、適切な雇用管理を行ったり、障害者のスキル向上や定着を支援する取り組みに対しても、助成金を活用できる場合があります。
これらの制度をうまく活用すれば、初期投資や継続的な支援にかかるコストの負担を軽減し、安定した雇用体制を構築できるでしょう。
障害者雇用の助成金について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
障害者雇用を始めた企業が抱えがちな課題

障害者雇用には多くのメリットがありますが、導入を進める上で、さまざまな課題に直面することがあります。ここでは、企業が障害者雇用に取り組む際に生じがちな課題を紹介します。
障害者雇用の課題について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
離職率の高さ
障害者雇用で課題となるのが、離職率の高さです。障害者の離職率が全体的に高い傾向がある理由として、職場の人間関係や雰囲気、賃金や労働条件に対する不満、仕事内容のミスマッチなどがあげられます。
障害への理解不足や配慮の欠如が、障害者の早期離職につながるケースも少なくありません。
また、障害者を雇用するには、時間や労力のほかに一定のコストがかかります。そのため、離職率を考慮した上で、採用後の定着支援をしっかり行うことが重要です。
社内の受け入れ態勢の構築
障害者を採用するだけでなく、安心して働ける社内環境を整備することも欠かせません。受け入れ体制が不十分なまま障害者雇用を進めると、能力を十分に発揮できなかったり、周囲とのコミュニケーションに課題が生じたりする可能性があります。
さらに、職場全体のモチベーションが低下するおそれもあります。社員から障害者への理解を得ることは容易ではありません。法律上の義務だからと一方的に押し付けるのではなく、障害者雇用のメリットを実感できる工夫が必要です。
障害者雇用の導入におけるコスト
障害者雇用を進める上で、受け入れ体制を整えるためのコストは、企業にとって大きな課題といえます。企業には、障害者が安心して働けるよう職場環境を整える配慮が求められており、法律によって義務づけられているのです。
例えば、バリアフリー対応のための職場環境の整備や、専用設備、支援ツールの導入、通勤支援、周囲の社員に向けた研修など、多くの初期投資が必要となる場合があります。
さらに、障害者に合わせた柔軟な勤務体制やサポートするための人件費も必要です。これらの金銭的な負担は企業規模によっては重く感じることもあり、障害者雇用をためらう要因にもなりかねません。
障害者雇用を成功させるポイント

障害者雇用を円滑に進めるには、事前準備と社内の理解が欠かせません。ここでは、障害者雇用を促進するポイントを紹介します。
経営層や人事部から意義を説明する
障害者を受け入れるには、事前に社内で理解を深め、不安を払拭しておく必要があります。まずは、経営層や人事部が障害者雇用の目的や意義を整理し、障害への正しい知識を持つことが重要です。
また、障害者を雇用する理由や進め方などを社員と共有しておきましょう。実際に障害者とともに働く社員の理解や協力がなければ、障害者の長期的な定着は難しくなるためです。
現場の準備が整わない状態で採用を進めてしまうと、後からさまざまな課題が出てくる可能性があります。受け入れ側の不安を減らすためにも、社内研修や情報共有の機会を設けることをおすすめします。
雇い入れる障害者本人へのヒアリングを行う
障害者に必要な配慮は、個人によって異なります。採用後は、本人と面談を行い、業務上の悩みや必要な支援などを具体的に把握しましょう。例えば、移動に車椅子を使う方には動線の確保、聴覚障害のある方には筆談などの配慮が有効です。
「障害者雇用促進法」により義務づけられた、障害者への合理的配慮を前提に、個別のニーズに応じた職場環境を整備することで、障害者の長期的な定着につながります。
障害者雇用促進法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
各種機関へ相談する
障害者雇用を進める際には、外部支援機関の活用もおすすめです。例えば、ハローワークでは、障害者専用窓口で職業相談や紹介などの支援を受けることができます。実際、多くの障害者がハローワークに登録しており、人材確保に向けた重要な接点となるため、まずはハローワークに相談すると良いでしょう。
また、地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援センターでは、さまざまな事例を知ることができ、職場づくりのヒントが得られます。初めて障害者雇用に取り組む企業にとって、こうした支援は心強い味方になるでしょう。
助成金を活用する
障害者雇用に伴う設備投資や人員体制の整備には、費用が発生する場合もあります。企業側の金銭的な負担を軽減するために、国が用意している各種助成金制度を活用しましょう。
例えば、障害者トライアル雇用助成金や特定求職者雇用開発助成金、障害者雇用納付金制度に基づく助成金などがあります。助成金を活用する際は、事前に申請条件を確認し、適切に手続きを行うことが重要です。
障害者雇用支援サービスも検討する
社内の受け入れ体制が整わない場合は、外部の障害者雇用支援サービスを検討するのもひとつの方法です。なかでも近年注目されているのが、農園型障害者雇用です。
企業が雇用主となり、給与や社会保険の責任を持つ一方、日々の業務管理やサポートは農園型障害者雇用支援サービスが担います。
企業と正式な雇用関係にあるため、法定雇用率の対象にもなり、企業の負担を軽減しながら雇用を実現できるのがポイントです。
農園型障害者雇用を検討するなら、「めぐるファーム」にご相談ください。
めぐるファームでは、都心からのアクセスに優れた施設内で、障害者の方々に農業を通じた就業機会を提供しています。日々の作業指導や生活面のサポートを行いながら、将来的には企業での就労につながるよう支援しています。
農園は年間を通じて快適な温度管理がされており、自然災害に強いトラス構造のハウスを採用しているため、安心して働くことが可能です。
また、障害者雇用の経験がない企業様でも安心して取り組んでいただけるよう、管理者向けの研修制度もご用意しています。
「めぐるファーム」の取り組みにご関心のある企業様は、ぜひ以下より詳細をご覧ください。
まとめ
障害者雇用を進めることで、企業イメージの向上やダイバーシティ経営の実現、人手不足への対応にもつながります。また、業務フローの見直しや効率化を図れるほか、税制優遇や助成金の活用も可能です。
一方で、障害者を受け入れるには、一定のコストや事前準備が必要です。そのため、企業と障害者の双方が安心して働ける環境を整えられるよう、社内で障害者雇用の意義を共有し、計画的な受け入れ体制を構築していきましょう。
本コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。