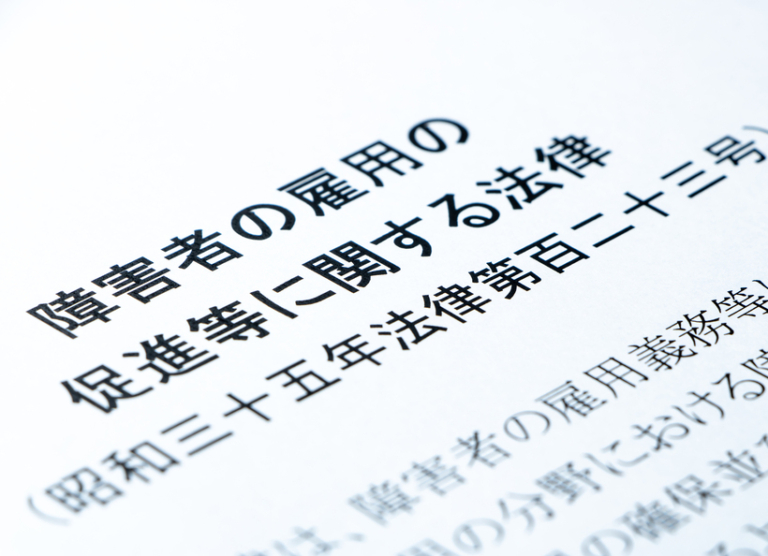障害者雇用促進法に従い、企業には定められた割合以上の障害者を雇用する義務があります。従業員の増加に伴い、法定雇用率の達成が課題になっている場合や、そもそも自社の規模で雇うべき人数がわからない場合もあるでしょう。
障害者雇用の計画立案には、単なる制度の理解だけでなく、自社の雇用義務数と実雇用率を正確に把握するプロセスが不可欠です。今回は、法定雇用率の仕組みや算定方法のほか、未達成の場合のリスクについても解説します。なお、このコラムでは「障害者の雇用の促進等に関する法律」を「障害者雇用促進法」として表記します。
障害者の法定雇用率とは?

初めに、法定雇用率の制度の趣旨や今後の動向について解説します。
障害者雇用促進法に基づく「法定雇用率」について
障害者の職業的な自立や職業の安定を目的とした障害者雇用促進法では、事業主に法定雇用率の順守を義務付けています。法定雇用率とは、事業主に求められる障害者の雇用割合です。
雇用と就業は、障害者が能力を発揮し、社会の一員として自立した生活を送るための軸として法律でも重視されています。
事業者に期待される役割は、社会的責任として雇用を通じて障害者を支援することです。働きやすい職場づくりに取り組むことで、事業者にも、法令遵守による社会的信用の向上やダイバーシティの推進などのメリットがもたらされます。
民間企業の法定雇用率は、以下の計算式で算出される数値やその他の要素を考慮して設定されています。
障害者雇用率 =(A+B)÷(C+D)
A:常用で働く障害者の数
B:失業中の障害者の数
C:すべての常用で働く労働者数
D:すべての失業者数
制度の対象となるのは、原則として障害者手帳を所持している方です。特殊法人や国および地方公共団体には、民間企業を下回らない雇用割合が求められます。
法定雇用率に関する法令については、こちらの記事をご覧ください。
事業主別の法定雇用率
法定雇用率は、業種や業態にかかわらず、全国一律に適用される基準です。令和6年4月から令和8年6月までは、次のように設定されています。
民間企業:2.5%
都道府県などの教育委員会:2.7%
国、地方公共団体、特殊法人:2.8%
各事業主には、法定雇用率を上回ることが求められます。下回った企業には、後述するペナルティが課される仕組みとなっています。なお、障害者の就労が困難な業種では、雇用義務が軽減される除外率制度もあります。
令和6年以降の法定雇用率
社会環境は変化しているため、法定雇用率はおおむね5年ごとに見直されます。
注目すべき点は、法定雇用率の引き上げと適用される事業主の範囲の拡大が、以下のように進められていることです。この背景には、誰もが社会参加できる共生社会の実現や、障害者の活躍の場の拡大などが望まれている現状があります。
| カテゴリー | 令和6年4月 | 令和8年7月 |
|---|---|---|
| 民間企業 | 2.5% (従業員数40名以上) | 2.7% (従業員数37.5名以上) |
| 都道府県などの教育委員会 | 2.7% (従業員数37.5名以上) | 2.9% (従業員数34.5名以上) |
| 国、地方公共団体、特殊法人 | 2.8% (従業員数36名以上) | 3.0% (従業員数33.5名以上) |
したがって、これまで対象外だった企業にも今後は適用される可能性が出てきます。
障害者雇用の法定雇用率を下回った場合のペナルティ

法定雇用率が未達成の場合、事業主にはどのようなペナルティが課されるのでしょうか。
まずは、ハローワークによる行政指導として、「障害者の雇入れに関する計画」の作成命令が出されます。指導は次のようなフローで進みます。
雇入れ計画作成・提出
↓
雇入れ計画の実施
↓
ハローワークからの適正実施勧告
↓
企業名公表を前提とした特別指導
この時点に至っても改善が見られない場合、厚生労働省のホームページに企業名が公表されるという措置が講じられます。企業名公表は、従業員の帰属意識の低下や企業イメージの悪化といったリスクを伴う重大なペナルティといえるでしょう。
そのほか、常用労働者が100人を超える企業で法定雇用率を下回っている場合には、不足する障害者1名につき月額5万円が課されます。
ここで留意すべき点として、納付金を支払っても障害者雇用の義務が免除されるわけではありません。そのため、事業主には引き続き障害者雇用の促進が求められます。
これらのペナルティを回避し、社会的責任を果たすためにも、制度を正しく理解し、計画的かつ着実に推進していくことが不可欠です。
障害者雇用納付金制度に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
出典:
厚生労働省「障害者雇用率達成指導の流れ」
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度の概要」
障害者の実雇用率を計算する方法

法定雇用率を達成するため、何名の障害者を雇うべきかを把握する際に用いられる数値が、雇用義務数と実雇用率です。続いて、これらの算出方法と計算時の注意点について解説します。
企業における雇用義務数と実雇用率の計算
雇用義務数とは、事業主が雇うべき障害者数です。実雇用率は、事業主が実際に採用している障害者の割合を指します。事業者には、これらの数値を基準に、法定雇用率を超える人数を採用できるように努力が求められます。
雇用義務数は、法定雇用率を用いて算出します。
雇用義務数 =(E+F×0.5)×法定雇用率
E:短時間労働者を除く常用労働者数
F:短時間労働者数
実雇用率の算出には、以下の計算式を使用します。
実雇用率 =(G+H×0.5)÷(I+J×0.5)
G:短時間労働者を除く常用勤務の障害者数
H:短時間で勤務する障害者数
I:短時間労働者を除く常用労働者数
J:短時間労働者数
実雇用率を計算するときの注意点
実雇用率の算出時には、前提となる常用雇用労働者や短時間労働者の定義、障害者数の換算方法についても理解しておく必要があります。
常用雇用労働者は、週の労働時間が20時間以上あり、1年以上雇われる見込みがある方を指します。このうち週の労働時間が30時間以上の方は「短時間以外の常用雇用労働者」、20時間以上30時間未満の方は「短時間労働者」と呼ばれます。
実雇用率を計算する際の障害者数の換算方法は以下の通りです。
| 週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 | 10時間以上20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 1名 | 0.5名 | – |
| 知的障害者 | 1名 | 0.5名 | – |
| 精神障害者 | 1名 | 1名※ | 0.5名 |
| 重度身体障害者 ・重度知的障害者 | 2名 | 1名 | 0.5名 |
※勤務時間が20時間以上30時間未満の精神障害者は、当分の間、雇い入れからの期間などを問わず、1名分に換算
そのほか、複数の事業所を有する企業では、各事業所で計算するのではなく、企業全体の合算で実雇用率を算出できます。特例子会社を設立している場合は、親会社の実雇用率との合算が可能です。
特例子会社とは、特別の配慮により障害者の雇用促進や安定的な就労を目指す子会社のことです。認定を経て設立すれば、雇用管理の促進や効率化が図れます。
障害者雇用の法定雇用率に不安があるときのポイント
「雇用率の達成が難しい」「社内環境の整備に不安がある」という企業では、次のような選択肢も検討してみましょう。
相談窓口を活用する
事業主への支援を提供する相談窓口として、以下のような機関があります。不安がある場合は、自社の状況に合わせて適切な機関に相談してみると良いでしょう。
| 相談窓口 | 支援内容 |
|---|---|
| ハローワーク | 全国544か所(令和7年度時点)。特性に合わせた職業紹介や職業指導のほか、事業主に向けた各種助成金の案内や申請受付、専門機関の紹介なども行う。 |
| 地域障害者職業センター | 全国47都道府県に設置。職業カウンセラーによる職業評価や職業準備支援、事業主への障害者雇用に関するアドバイスなど、より専門的な支援を提供する。 |
| 障害者就業・生活支援センター | 全国339か所(令和7年6月時点)。生活面と就業面の両方から包括的な支援を行い、事業主からは雇用管理の相談も受け付ける。 |
| 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) | 雇用管理や職場環境整備のための相談、助言など、事業主の負担軽減につながる支援を提供する。 |
農園型障害者雇用を検討する
近年、新たな雇用の形として注目を集めているのが、専門の支援業者から借りた農園で障害者が勤務する「農園型障害者雇用」です。
障害者の方は、農園側の各種サポートを受けつつ農園での作業に従事しますが、管理監督は雇い主が行うため、その企業や組織の法定雇用率に含まれます。
全国で10社~20社程度の農園型支援業者が存在し、すでに1万名ほどの人が、この仕組みのもとで働いています。
農園型障害者雇用支援サービスのうち、都心からアクセスの良い立地に快適な環境を整備しているスマート農園が「めぐるファーム」です。
導入企業の管理者向け研修や本人への入社研修なども充実しており、初めて障害者雇用に取り組む企業や組織も安心して導入できるサポート体制が整っています。
障害者が無理なく活躍できる場となるだけでなく、自社のオフィス環境では制約がある企業や組織にとっても、法定雇用率を達成するための有効な手段となるでしょう。関心のある人事担当者様は、ぜひこちらをご覧ください。
まとめ
企業の社会的責任の観点からも障害者雇用の重要性は増しており、法定雇用率の対象となる企業の範囲も段階的に拡大しています。法定雇用率の達成は単なる義務ではありません。積極的に取り組めば、社会貢献を果たし、新たな企業価値を生み出すための良い機会となり得ます。
今回紹介した相談窓口をはじめ、農園型障害者雇用のような新しいサービスを活用することもぜひご検討ください。自社の状況に合わせたアプローチで、より良い形での職場のあり方が実現されるはずです。
本コラムに記載の内容は、2025年8月4日時点の情報に基づきます。

Profile
著者プロフィール
めぐるファーム編集部
障害者の雇用が少しでも促進されるよう、企業担当者が抱いている悩みや課題が解決できるようなコンテンツを、社内労務チームの協力も得ながら提供しています。